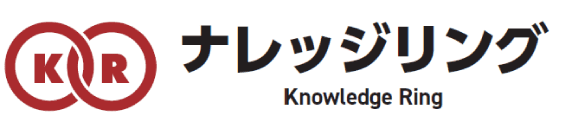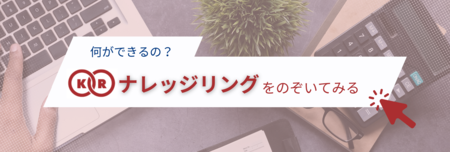ノウハウ・ナレッジの違いを徹底解説!
FAQ活用で“知ってる”を仕組化する方法

こんにちは。
ナレッジリングのマーケティング担当の谷知です。
「ノウハウ」や「ナレッジ」という言葉をよく耳にするものの、
その違いや活用方法が曖昧なまま、社内共有が進んでいませんか?
本記事では、
ノウハウとナレッジの意味や違いをわかりやすく解説し、
業務効率化につながる活用方法や仕組み化のポイントを詳しく紹介します。
また、FAQというツールを通して、
社内の情報共有を一歩進めるヒントもお伝えします。
クラウド型FAQツール「ナレッジリング」がおすすめ!
- 直感的なデザインで誰でもカンタンに操作できる!
- 業界最安クラスだから導入しやすい!
- 導入後もサポート付きで安心!
機能の特徴や導入事例をご紹介しております。無料プランやデモもご用意しておりますので、ぜひご覧ください。
ノウハウとは?意味と具体例をわかりやすく解説

ノウハウとは、
業務や作業をスムーズに進めるための実践的な知識や手順のことです。
まずはノウハウの定義や、
具体的にどのような形で社内に存在しているのかを紹介します。
ノウハウの基本的な意味とは
ノウハウとは、
経験に基づいて蓄積された実践的な知識やスキルのことを指します。
単なる理論ではなく、
実際に業務で成果を出すための「やり方」が中心です。
例えば、社内のルーティン業務の進め方や、
顧客対応のポイントなどがノウハウに該当します。
こうしたノウハウは、属人的になりやすいため、
いかに形式知化して共有するかが重要です。
ノウハウの具体例(業務マニュアル・営業トーク・社内手順など)
ノウハウには、
さまざまな業務の中に散りばめられた
「暗黙のルール」や「工夫」が含まれます。
例えば、
営業トークのタイミングや言い回し、
スムーズに経理処理を進める方法、
マニュアルに書ききれない細かな操作手順などです。
これらは一見個人の感覚に頼っているように見えますが、
実は社内で共有することで全体の業務品質を高める重要な資産となります。
ノウハウが重要視される理由
ノウハウは業務を遂行する上で、
差別化や効率化に大いに貢献します。
特にベテラン社員が持つノウハウは、
短時間で業務を処理したり、
ミスを未然に防いだりする力があります。
こうしたノウハウを個人に留めるのではなく、
チームや組織全体で活用することが、
全社の生産性向上や人材育成にもつながります。
▼ こちらの記事もおすすめ ▼
チームで成功するためのノウハウ共有術~ツール選びの基本とコツ~
ナレッジとは?ノウハウとの違いを徹底比較

ナレッジとは、個人や組織が蓄積した知識や情報を集めたものです。
ここでは、ナレッジの定義や分類、
ノウハウとの違いについて詳しく見ていきます。
ナレッジの定義と分類(暗黙知と形式知)
ナレッジは、
大きく「暗黙知」と「形式知」に分類されます。
以下、それぞれ説明します。
- 暗黙知
言語化・文書化されていない知識であり、経験や感覚に基づくもの
- 形式知
マニュアルや手順書のように明文化された知識のこと
企業では、この形式知をいかに整備して共有するかが、
生産性向上やミスの防止に直結します。
ナレッジを活用するためには、
暗黙知と形式知を意識することが大切です。
▼ こちらの記事もおすすめ ▼
ナレッジとは?意味・定義・活用方法まで初心者にもわかりやすく解説
ノウハウとナレッジの違い
ノウハウとナレッジは混同されやすいですが、
ノウハウは実務に即した「やり方」、
ナレッジは知識そのものの「蓄積」が主な違いです。
ノウハウはナレッジの一部と捉えることもできますが、
ノウハウはさらに具体的で即効性のある情報のことを指します。
例えば
「この手順でやればうまくいく」といったものがノウハウであり、
その背景にある理論や成功事例を含む情報群がナレッジです。
混同しやすい用語との違い(スキル・知識・知見)
ナレッジやノウハウに似た言葉に
「スキル」「知識」「知見」などがあります。
- スキル:主に実践的な能力や技術のこと
- 知識 :学習や教育によって得られた情報のこと
- 知見 :特定の領域で深められた知識や考察のこと
これらは相互に関係していますが、
ナレッジはより広く、
組織的に活用するための土台となる情報群を指します。
それぞれの正確な使い分けが、
情報共有の質を高めることにつながります。
ノウハウやナレッジが共有されないとどうなる?

ノウハウやナレッジが共有されずに属人化したままだと、
組織全体のパフォーマンスに大きな影響を及ぼします。
ここでは共有されないことによる主なリスクを紹介します。
属人化による業務の非効率
特定の人しかできない業務が増えると、
その人の不在時や退職時に業務が止まってしまうリスクがあります。
これが「属人化」です。
属人化が進むと、新人への引き継ぎにも時間がかかり、
教育に費やす時間も増えてしまいます。
また、ノウハウを蓄積・共有する仕組みがないと、
同じ失敗や試行錯誤が何度も繰り返され、
チームや企業全体としての業務効率が低下します。
情報ロス・引き継ぎトラブルのリスク
情報が個人の頭の中や私的なメモにしか存在しない場合、
部署異動や退職といったタイミングで
重要なノウハウが失われてしまうことがあります。
また、引き継ぎの際に抜け漏れが発生しやすく、
業務の停滞やトラブルの原因になります。
新人教育や問い合わせ対応の負担増
ノウハウやナレッジが文書化・共有されていない職場では、
新人が何かを覚えるたびに先輩社員の手を借りなければなりません。
また、同じような質問への対応が繰り返されるため、
教育係やヘルプデスク担当の負担が大きくなります。
よくある質問(FAQ)をあらかじめ整備しておくことで、
教育の効率化と問い合わせ対応の省力化が可能になります。
▼ こちらの記事もおすすめ ▼
ノウハウ・ナレッジを活かす仕組みづくりのポイント

ノウハウやナレッジを有効活用するためには、
単なる情報の蓄積ではなく、
活かすための仕組みづくりが必要です。
ここでは、情報共有を成功させるための実践的なポイントを紹介します。
なぜ情報共有はうまくいかないのか?
情報共有がうまくいかない理由の多くは、
溜め込んだノウハウやナレッジが「使われない仕組み」にあります。
ノウハウやナレッジを記録しただけで満足し、
それを活用する導線や仕組みが整備されていないケースが多く見られます。
例えば、
- 共有フォルダの中にある情報が見つけにくい
- 誰がどこに記録するかのルールが曖昧
などという状況が挙げられます。
共有された情報が「使われる仕組み」こそが、
ノウハウとナレッジ活用の鍵です。
共有の第一歩は「形式知化」と「検索性」
ナレッジを共有するための第一歩は、
頭の中にある情報(暗黙知)を言語化・可視化すること、
つまり「形式知化」です。
それと同時に重要なのが、
誰でも必要な情報をすぐに見つけられる「検索性」です。
いくら情報が蓄積されていても、
探しにくければ意味がありません。
ノウハウやナレッジを共有するツールを導入する際は、
情報を階層化したり、タグやカテゴリを活用するというような、
形式知化と検索性を両立させる工夫が求められます。
属人化を防ぐには「使われる仕組み」が必要
属人化を防ぐには、
誰もが情報を記録・活用しやすい仕組みが必要です。
そのためには、
ツールの使いやすさや運用ルールの明確化が重要です。
また、情報共有の文化を根付かせるには、
「共有するメリット」が実感できるつくりが欠かせません。
例えば
「検索すればすぐ出てくる」
「質問しなくても答えがある」
というような状態をツールの中で設けることで、
自然と情報共有の好循環が生まれます。
▼ こちらの記事もおすすめ ▼
ナレッジ共有とは?ツールを効果的に活用して業務を加速させよう
FAQでノウハウとナレッジを“知っている”から“使える”に変える!

FAQは、
ノウハウやナレッジを形式知として蓄積し、
誰でも活用できる形で共有するのに適した仕組みです。
この章では、
FAQの特性や、実際の成功事例、
活用を進めていく際の方法について解説します。
ノウハウ・ナレッジの「見える化」にFAQが最適な理由
FAQ(よくある質問)は、
現場で繰り返される疑問やトラブルに対して、
あらかじめ答えを用意しておく仕組みです。
Q&A形式で構成されているため、
情報を簡潔かつ目的別に整理でき、
閲覧者にとっても検索・理解がしやすいのが特長です。
特に、暗黙知になりがちな業務上のノウハウを
言語化・体系化する上で非常に効果的な方法です。
また、質問される前に答えを用意できるため、
教育にかかる時間や問い合わせ対応の負担を軽減するツールとしても有効です。
社内FAQの成功事例に学ぶ活用ポイント
例えば、
経理・人事・情報システムなどのバックオフィス部門で
社員から寄せられる質問の多くを
社内のFAQとしてまとめて設置することで、
回答の標準化と対応スピードの向上を実現することができます。
FAQを社内で活用するポイントは
「誰が見てもすぐにわかる表現」と
「更新しやすい仕組み」を意識することです。
また、FAQは一度作って終わりではなく、
継続的な見直しと改善が運用成功の鍵となります。
▼ こちらの記事もおすすめ ▼
FAQを軸にしたナレッジマネジメントの始め方
社内でナレッジの有効活用(ナレッジマネジメント)を始める際には、
まずは過去の問い合わせ履歴や
新人からのよくある質問を洗い出すことから始めましょう。
これらをベースにFAQを作成すれば、
即効性のある情報をそろえることができます。
また、FAQを一元的に管理できるツールを使えば、
検索性・更新性・アクセス解析などもスムーズに行えます。
さらに、社内での運用方法やルール
(誰が作る/誰が更新する/どう通知するか)
を明確にすることで、
ナレッジマネジメントが定着しやすくなります。
▼ こちらの記事もおすすめ ▼
ノウハウ・ナレッジ共有におすすめのFAQシステム「ナレッジリング」

FAQの仕組みを実現するには、
情報を見える化し、誰でも使えるようにするツール選びが重要です。
ここでは、社内FAQの導入に特化した
クラウド型FAQシステム「ナレッジリング」の特長や導入のメリットをご紹介します。
「ナレッジリング」でできること
ナレッジリングは、
社内FAQを簡単に構築・運用できるFAQシステムです。
質問と回答をセットで登録・管理できるのはもちろん、
統計モニタリングやキーワード分析、検索時のサジェスト機能など
ナレッジの「使われやすさ」を重視した機能が充実しています。
誰でも簡単に更新できる直感的な操作性で、
情報の鮮度を保ちながら、
社内のノウハウを整備していくことが可能です。
社内向けFAQの活用事例
実際にナレッジリングを導入した企業では、
人事や情報システム部門の問い合わせ対応業務が大幅に効率化されています。
特に社員数の多い企業では、
標準化された情報を提供するツールとして
ナレッジリングを導入することで
業務軽減や効率化につながっています。
▼ 他社の成功事例を見てみる ▼
ナレッジリングが選ばれる理由と他ツールとの違い
ナレッジ共有ツールには、
社内Wiki、ファイル共有、マニュアルツールなどがありますが、
それぞれにメリット・デメリットがあります。
- 社内Wiki
自由度が高い反面、構造が複雑化しやすく定着しにくい
- ファイル共有
ドキュメントの格納には向いていても、Q&A形式にすると使いにくい
一方でナレッジリングは、FAQ形式に特化することで、
「情報を探しやすい」
「誰でも書きやすい」
「すぐに使える」
仕組みを提供することができます。