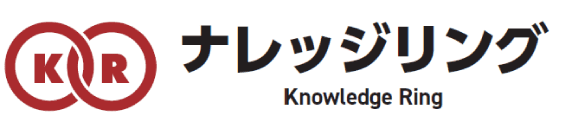ナレッジマネジメントには社内FAQシステムの活用がおすすめ

こんにちは。
ナレッジリングのマーケティング担当の谷知です。
社内で蓄積した知識や情報といったナレッジを共有したい、有効活用したい…
でもどうしたらいいかわからないと頭を抱えている担当者の方々も多いと思います。
ナレッジ共有の方法はさまざまですが、
今回は社内FAQシステムを活用したナレッジマネジメントをご紹介します。
ナレッジという資産を無駄にしないためにも、ぜひ参考にしてみてくださいね。
ナレッジマネジメントについて

ナレッジマネジメントとは
組織内での知識や情報を有効に活用するための管理手法のことを言います。
組織内で蓄積された情報や経験、ノウハウなどの知識は「ナレッジ」と呼ばれます。
ナレッジを共有・蓄積し効率的に活用することで、組織の業務効率や競争力を高め、
新入社員や若手社員に向けた人材育成にも役立ちます。
組織においてナレッジマネジメントを実施することは、組織の成長や発展に不可欠なのです。
ナレッジマネジメントの目的と手段、タイプ

ナレッジマネジメントの目的と手段
ナレッジマネジメントを社内で活用するにあたり、まずは目的と手段に分けて考えていきます。
1)知識資産活用目的
【 改善 】 <- -> 【 増価 】
業務の効率化を求める「改善」か
事業拡大や新事業など更に価値を高めるための「増価」か
2)知識資産活用手段
【 集約 】 <- -> 【 連携 】
分散されたナレッジを「集約」して活用するか
さまざまなナレッジの組み合わせを「連携」して活用するか
さらに「目的」と「手段」の組み合わせにより、
ナレッジマネジメントは4つのタイプに分類されます。
次項で解説します。
ナレッジマネジメント 4つのタイプ
ナレッジマネジメントは以下の4つのタイプに分類されます。
1.[ 改善 ] × [ 集約 ] → ベストプラクティス共有型
2.[ 改善 ] × [ 連携 ] → 専門知ネット型
3.[ 増価 ] × [ 集約 ] → 知的資本型
4.[ 増価 ] × [ 連携 ] → 顧客知共有型
タイプを見ただけでは、自社の悩みや課題解決方法がどれにあたるか、
いまいちわかりませんよね。
お悩み別にタイプを当てはめて解説していきます。
お悩み別 ナレッジマネジメントタイプ診断

自社でのナレッジ共有に悩みを持つ方向けに、
お悩み別に解決できるナレッジマネジメントタイプを当てはめてみました。
自社の悩みや課題、解決していきたい方向などに近いタイプを探してみてください。
お悩み①去の成功事例や社員の知識などを共有できず、早期の組織成長が目指せない
→解決タイプ:ベストプラクティス共有型(改善×集約)
過去の成功事例や、優秀な社員の知識・ノウハウなどを形式知化し組織レベルで活用することで、
共有したいナレッジをマニュアル化し、ナレッジ共有ツールに蓄積しながら、
組織全体のスキルの底上げを目指します。
ナレッジ共有は、優れたノウハウを持つ社員がいても組織で共有されなければ意味がありません。
しかし、自身の評価に影響するため他人に教えたくない、
多忙のためにマニュアル化する時間を確保できないなど、
ナレッジ共有の推進を阻む要因も存在します。
このような場合は、組織のあり方も含めて、ナレッジ共有を確立する方法を検討する必要があります。
ナレッジ共有を推進するためには、組織全体で意識を高め、
効果的な情報共有ツールの導入や、ノウハウを共有するための文化づくりが必要です。
お悩み②専門知識を持つ人はたくさんいるが、意見を集約できない
→解決タイプ:専門知ネット型(改善×連携)
専門知ネット型では、専門家の知識をデータベース化し、FAQなどの形で活用することが一般的です。
また、「Know Who(ノウフー)」という、
「誰が何に詳しいのか」「業務の経験者やエキスパートについて情報」を
まとめている仕組みを導入することがあります。
その中で専門家同士が交流する機会が生まれ、新しい知見が生まれることもあります。
さらに、専門家たちが積極的に情報を共有するようにするために、
ナレッジ共有ツールなどの適切なプラットフォームの導入や、コミュニケーションの改善など、
様々な要素を組み合わせた戦略が必要になります。
ただし、専門知ネット型でナレッジ共有が成功するかどうかは、
知識を持つ側からのアウトプットに掛かっているため、
専門家から知識を引き出すための環境作りが重要です。
お悩み③膨大な知識を役立てられていない
→解決タイプ:知的資本型(増価×集約)
組織に蓄積された膨大な知識データを経営戦略に役立てる方法です。
知的資本型は、データウェアハウスやデータマイニングなどの専用ツールを使用して、
膨大なデータを多角的に分析し、新しい価値を生み出すことを可能とします。
分散されたナレッジを集約し整備することにより、収益アップを目指す手法です。
お悩み④顧客の対応履歴やアンケート回答などを活かしきれていない
→解決タイプ:顧客知共有型(増価×連携)
顧客知共有型は、同じ連携型である専門知ネット型と同様、
過去の対応事例のデータベース化や、顧客対応を標準化するFAQ化が、
ナレッジ共有の有効な手段として用いられます。
過去の対応履歴を蓄積することで、
同様の問い合わせに対する解決スピードの向上を見込めたり、
顧客の声を直接反映することで顧客満足度向上に繋がったりと、
企業の信頼性を高めることができます。
いかがでしたか?
お悩み別のタイプ診断がわかったところで、
次は社内FAQシステムを活用したナレッジマネジメントの構築方法を紐解いてみましょう。
社内FAQシステムがナレッジマネジメントの成功を導く

ナレッジ共有の必要性や課題を解決していくために、
次は社内FAQシステムを活用して自社のナレッジマネジメントを最大化する方法をご紹介します。
FAQシステムとナレッジマネジメントの関係性についても解説していきます。
FAQシステムとは
FAQシステムとは、
よくある質問とそれに対する回答を集約し検索できるようにしたシステムのことです。
FAQは「よくある質問」「Q&A」などとも呼ばれ、
頻繁にお問い合わせのある質問に対する回答を用意することで、
利用者の疑問を解消する役割を持っています。
FAQシステムとナレッジマネジメントの関係性
FAQシステムがナレッジマネジメントの一環として利用される理由には、
主に次のような点が挙げられます。
①簡易的に情報へのアクセスでき、迅速に問題が解決できる
FAQシステムでは、ユーザーからのよくある質問に対して、
正確な情報を提供できるため、
ユーザーは迅速かつ簡単に必要な情報にアクセスすることができます。
また、それに伴いユーザー自身が問題を解決することができるため、
ユーザーの満足度向上やサポート側の負荷軽減につながります。
②組織全体での情報共有が容易にできる
FAQシステムでは、繰り返し発生する質問への回答を自動的に提供します。
自動的に対応していくことで、組織内の業務効率が向上します。
また、FAQシステムが効果的に機能すると、今まで人が担ってきたサポート減少し、
人的リソースの節約へとつながります。
③トレーニングと教育のサポート
FAQシステムは新しい製品やサービスに関する社員への
トレーニングや情報共有にも活用できます。
社員が新しい情報を素早く理解できることで、
ユーザー側からの質問や回答を事前に準備することができます。
以上のように、FAQシステムとナレッジマネジメントの関係性は、
効率的な情報提供と業務効率の向上に役立てることができるのです。
社内FAQシステムの活用がナレッジマネジメントの成功につながる理由
社内FAQシステムを活用することがなぜナレッジマネジメントの成功につながるのか、
主な理由は次の3点です。
理由①適切な導入計画を練ったから
FAQシステムを導入する際には、社内のニーズや目標とする形を考慮する必要があります。
共有すべき情報をしっかりと取り入れ、利用しやすい内容に整備しましょう。
理由②コンテンツを定期的に更新できるから
FAQシステムは、導入後もコンテンツを定期的に更新・精査することが大切です。
変化する環境に迅速に適応するためにも、
情報が常に最新かつ利用可能な状態であることを心がけましょう。
理由③利用者から定期的にフィードバックをもらい、改善していけるから
利用者からの定期的にフィードバックをもらいながら、
コンテンツを改善する仕組みを構築していくことが大切です。
利用者のフィードバックは実質的な情報として価値があるため、
ナレッジマネジメントの成功に直結するからです。
ナレッジマネジメントは組織の発展に不可欠な要素のひとつです。
社内FAQシステムをうまく活用して、ナレッジマネジメントを成功させましょう。
おすすめの社内FAQシステム「ナレッジリング」のご紹介
社内FAQシステムを活用することが
ナレッジマネジメントの成功につながることをお伝えしました。
自社の状況に近い解決策は見つかりましたか?
ここで、おすすめの社内FAQシステム「ナレッジリング」をご紹介しましょう。
ナレッジリングは、いつでも・どこでも・カンタンな操作で社内の情報共有を促進し、
効率的に業務を遂行するための機能や特徴を備えたFAQシステムです。
社内FAQに役立つ主な特徴は以下の通りです。
- 【特徴①】ITリテラシーが高くない社員でもすぐに利用できる
ナレッジリングは、誰でも簡単に利用できることが特徴です。
シンプルな画面構成のため、直感的な操作でキーワード検索やカテゴリー検索ができ、
必要な情報にすぐにアクセスすることができます。

<ナレッジリングの画面>
- 【特徴②】情報が見つかりやすい全文検索機能によって業務をスムーズに進められる
ナレッジリングは全文検索機能に対応しているため、
キーワード検索の際にFAQシステム内に登録されたファイルの中身まで見つけることができます。
FAQを検索するのと同時にマニュアルや資料などのファイルも検索するため、
情報が見つかりやすいことが特徴です。

<FAQのテキストとファイル内テキストを同時検索している例>
- 【特徴③】さまざまな分析機能を備えていて社内FAQを改善しやすい
ナレッジリングには、いつ・誰が・どのような操作をしたのかを常に記録します。
また、キーワード検索分析では、検索回数が多いキーワードだけでなく、
検索が一致しなかったキーワードも確認できるので、
システム内に足りていない情報も把握することができます。
これらの情報から、社内FAQシステムがどのように利用されているか詳細を分析することができ、
社内FAQの品質改善に役立てることができます。

<キーワード分析>
社内FAQシステムを導入するなら・・・
| 【おすすめツール】
圧倒的コスパでナレッジ共有を促進!クラウドFAQシステム「ナレッジリング」
|