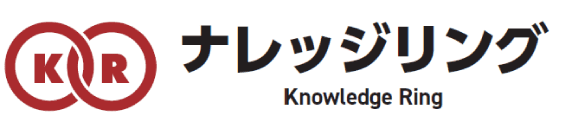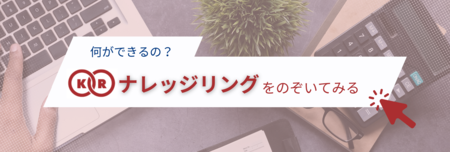もう迷わない!
マニュアル作成がラクになる“使えるツール”の選び方ガイド

こんにちは。
ナレッジリングのマーケティング担当の谷知です。
多くの企業が業務の効率化やナレッジの共有を目的に
マニュアルを用意しますが、
「マニュアル作成が進まない」
「せっかく作ったのに使われない」
といった悩みを抱えています。
実際、マニュアル作成は時間と労力がかかるうえ、
完成しても運用されなければ意味がありません。
また、現場ごとに情報が属人化していると、
マニュアルに反映すること自体が難しくなります。
この記事では、
マニュアル作成がうまくいかない理由を明らかにしたうえで、
基本的なプロセスや定着のコツ、
さらにマニュアルとして使えるツールの選び方を具体的に解説します。
- 直感的なデザインで誰でもカンタンに操作できる!
- 業界最安クラスだから導入しやすい!
- 導入後もサポート付きで安心!
機能の特徴や導入事例をご紹介しております。無料プランやデモもご用意しておりますので、ぜひご覧ください。
なぜマニュアル作成がうまくいかないのか?

マニュアルの活用に向けて取り組んでいるにもかかわらず、
うまく活用されないケースが多く見られます。
その背景には、
業務の属人化や作成コストの高さ、活用されない構造など、
いくつもの要因が潜んでいます。
この章では、
マニュアル作成が失敗する代表的な理由を具体的に掘り下げていきます。
情報が属人化している
マニュアル作成の第一の障壁は、
情報が個人に依存してしまっている「属人化」です。
担当者の頭の中にしかないノウハウや手順は、
外に出されなければマニュアル化できません。
例えば、ベテラン社員が独自のやり方で業務を回していた場合、
本人以外には詳細がわからず、
文書化しようにも情報が不足します。
このようなケースでは、
本人が忙しい・文書化に慣れていないなどの理由で
作成が後回しにされがちです。
また、引き継ぎが口頭で済まされる文化があると、
マニュアルの必要性すら認識されないこともあります。
こうした属人化は、
業務の標準化やスキルの平準化を妨げる大きな要因となります。
▼ こちらの記事もおすすめ ▼
作成の手間が大きく、後回しにされがち
マニュアルを作るには、
業務の洗い出し、フローの整理、文書構成の決定、
文章作成、見直し、共有…と多くのステップがあります。
そのため、
「忙しい業務の合間にマニュアルを作る余裕がない」という
現場の声も少なくありません。
また、「誰が作るのか」という役割分担が曖昧だと、
責任の所在が不明瞭になり、
結局誰も着手しないまま放置されるケースもあります。
一度作ったとしても、
「どこまで細かく書くべきか」
「図解を入れるべきか」
など判断に迷い、
作業が止まってしまうこともあるでしょう。
作成を専門職に任せる体制がない場合、
知識のある現場担当者が自力で進める必要があり、
心理的なハードルも高くなりがちです。
更新・改善の仕組みがない
マニュアルは、一度作ったら終わりではありません。
業務内容の変更や手順の見直しに合わせて、
継続的な更新が必要です。
しかし、多くの現場では「作って終わり」になっており、
見直しのルールが決まっていないケースが散見されます。
その結果、内容が実態とズレてしまい、
「結局使えない」と判断されてしまうのです。
例えば、
「最新情報は別の場所にある」
「手順が現場で変わっているのに反映されていない」
などの状況が続けば、
ユーザーはマニュアルそのものを信用しなくなります。
こうした形骸化を防ぐためには、
定期的な見直しのスケジュールや、更新履歴の管理、
フィードバックを受け取る仕組みを整備することが欠かせません。
完成しても使われない理由とは?
「せっかく時間をかけて作ったマニュアルが、誰にも読まれていない…」
そんな嘆きもよく聞かれます。
その理由はさまざまですが、
主に以下のような課題が挙げられます。
- マニュアルの場所がわかりずらく、必要なときにすぐ見つけられない
- 内容が古くなっている
- 現場の実態に即していない
- 読みづらい
使われるマニュアルにするには、
「探しやすさ」と「読みやすさ」の両方が欠かせないのです。
マニュアル作成の基本プロセスと失敗しない手順

マニュアルを効果的に作成・活用するには、
明確な目的設定や構成の整備、
運用の仕組みづくりが不可欠です。
この章では、
誰でも実践できるマニュアル作成の基本プロセスと、
失敗を避けるための実践的な手順をご紹介します。
目的と対象を明確にする
マニュアル作成の出発点は、
「何のために」
「誰のために」
作るのかを明確にすることです。
例えば、
社内研修用のマニュアルであれば新入社員向けに、
業務引き継ぎ用であれば次の担当者向けに、といったように
目的と対象によって必要な情報の重要度やトーンも変わってきます。
目的が曖昧なまま進めてしまうと、
無駄に詳細すぎたり、逆に情報が足りなかったりと、
読み手にとって使いにくいマニュアルになってしまいます。
作成前に
「どんな場面で参照されるのか」
「読んだ人にどんな行動をしてほしいのか」
を具体的にイメージしておくと、
内容の設計がスムーズになります。
構成やテンプレートを整備する
マニュアルの質を左右するのが、構成やテンプレートの統一です。
例えば、
「目的」「手順」「注意点」「補足」といった
定型フォーマットを用意しておけば、
作成者の負担も減り、
読み手にとっても内容を把握しやすくなります。
また、視覚的にもわかりやすいよう、
見出し階層やフォントサイズ、
画像・スクリーンショットの使い方などをガイドラインとして定めておくと、
マニュアル全体のクオリティが安定します。
チーム内でテンプレートを共有しておくことで、
「誰が作っても同じ形式」という一貫性が生まれ、
属人化の解消にもつながります。
継続的な運用フローを考える
マニュアルは作るよりも運用こそが一番重要と言えます。
業務は日々変化するため、
マニュアルの内容も定期的に見直し、更新する必要があります。
そのためには、
「誰が」
「どのタイミングで」
「どのように」
更新するのか、
運用ルールをあらかじめ設けておくことが不可欠です。
例えば、
業務変更があった際に担当者が更新し、
チーム内レビューを経て公開するというフローを設けることで、
常に最新の情報が反映されます。
また、更新履歴を残しておけば、
変更の経緯が追えるため、トラブル時の対応にも役立ちます。
▼ こちらの記事もおすすめ ▼
マニュアル作成の方法とコツを完全ガイド ~失敗しない手順とポイントを解説~
マニュアルの改善を目的にしたツールの導入も有効
属人化の解消や、更新・検索のしやすさを考えると、
ツールでの情報整備も効果的です。
例えばFAQツールであれば、質問単位で簡潔に情報を切り出せるため、
必要な情報にすぐアクセスできますし、更新も容易です。
最近では、FAQ管理に特化したツールも登場しており、
ナレッジ共有のハードルを大きく下げてくれます。
マニュアルとFAQを組み合わせることで、
「調べやすく、使いやすい」情報共有の仕組みを実現できます。
マニュアルを現場で定着させるには?

マニュアルは「作ったら終わり」ではなく、
現場で定着し、活用されることが本来の目的です。
そのためには、ツール選定以上に
「運用ルール」や「社内浸透」の工夫が重要となります。
本章では、定着のための具体的な施策を紹介します。
ツールだけでなく「運用ルール」が重要
マニュアルの運用において見落とされがちなのが、
「運用のルールを定めること」です。
「ツールを導入すれば自然とマニュアル文化が根付く」と考えるのは危険で、
実際には“誰が何をいつ更新するか”といったルールがないと、
ツールも形骸化してしまいます。
例えば、
作成・更新のフローを明文化し、リーダーや担当者を明確にする、
さらに、定期的な見直しのスケジュールを設定することで、
属人化を防ぎ、継続的な改善が可能になります。
社内浸透の工夫(教育・導線づくり)
せっかくマニュアルを整備しても、
社内に浸透しなければ意味がありません。
まず重要なのは、
「マニュアルを使うメリット」をしっかり伝えることです。
業務の効率化や属人化の回避など、
現場にとってのメリットを実感してもらうことで、
社員が自発的にマニュアルを利用するようになります。
さらに、新人研修の一部としてマニュアルの活用方法をレクチャーしたり、
社内で使っているツール類のトップページにマニュアルへの導線を設けるなど、
アクセスしやすい環境づくりも効果的です。
「使ってもらうための仕組み」づくりは、
マニュアルを「読む文化」を社内に根付かせる第一歩です。
改善を続けるPDCA体制の整備
マニュアルは常に“今の業務に合っているか”を検証し、
改善していくことが求められます。
そのためには、
PDCA(Plan-Do-Check-Act)サイクルを回す体制が欠かせません。
例えば、半年ごとに棚卸しや社内アンケートを実施し、
「どのマニュアルが役立っているか」
「どこが分かりにくいか」
といったフィードバックを収集しましょう。
その結果を基に改訂を行うことで、
マニュアルはより実用的なものになります。
改善を習慣化することで、
マニュアルが“生きたドキュメント”として定着します。
▼ こちらの記事もおすすめ ▼
マニュアル活用を評価に反映させる仕組み
マニュアルを“読む・使う”文化を根付かせるためには、
「使うことが評価につながる」仕組みを導入するのも効果的です。
例えば、
- マニュアルを参照して対応したケースを月次レポートに記載する
- 活用頻度の高いマニュアル制作者を社内で表彰する
というように、
「マニュアルの活用が価値として認識される」制度づくりになることがポイントです。
さらに、マニュアル改善の提案や
フィードバックを提出した社員にインセンティブを与える仕組みも有効です。
「書く人」「読む人」双方が関わることで、
マニュアルは一方通行ではなく、組織全体で育てる“共創資産”となります。
マニュアル作成ツールの選び方ガイド

マニュアル作成ツールにはさまざまな種類があり、
それぞれ特性が異なります。
目的や利用シーン、使いやすさに応じた選定を行うことが、
導入成功のカギとなります。
この章では、
マニュアル作成ツールの選び方を
ポイントをおさえながら、わかりやすく整理します。
選び方①目的・用途別に選ぶ
マニュアル作成ツールは多種多様で、
選び方は「何を達成したいか」がポイントです。
- ドキュメント型
新人教育や業務フローの共有に最適
- Q&A形式のFAQツール型
問い合わせ対応の効率化や顧客向けFAQとして活用可能
- Wiki型
チームでの共同編集やコメント機能を重視する場合は最適
目的と用途を明確にした上で、
機能がそれにマッチしているかをチェックしましょう。
選び方②社員の使いやすさで選ぶ
ツールの使いやすさも選び方の大きなポイントです。
ITリテラシーに差がある社員が多い場合、
直感的に操作できることや
スマホ対応があるかどうかは大きなポイントです。
複雑すぎるツールは使われなくなるリスクが高いため、
ツールを正式に導入する前に、
操作性や検索のしやすさ、
情報の見つけやすさを必ず検証してください。
また、閲覧だけでなく編集も簡単にできるか、
権限設定が柔軟かどうかも重要な選定基準です。
選び方③導入〜定着のしやすさで選ぶ
ツールの導入のしやすさやサポート体制についても
運用側としては見逃せない選び方のポイントです。
初期設定やテンプレート整備、
既存データの移行がスムーズに行えるか、
サポートが充実しているかを確認しましょう。
さらに、ツール定着のための研修やマニュアルが用意されているか、
使い方の改善提案などの支援があるかも選ぶ際に重要です。
導入後の運用が継続できるかどうかは、
ツールの機能以上に重要な要素となります。
次の章では、
マニュアル作成ツールの種類とそれぞれの特徴を解説します。
自社の目的に合ったツールの選び方の参考にしてください。
▼ こちらの記事もおすすめ ▼
マニュアル作成ツールを活用しよう! ~「わかりやすい」マニュアルをFAQで効率的に作る方法~
マニュアル作成ツールの主な種類と特徴

マニュアル作成ツールには、
ドキュメント型、社内Wiki、FAQツールなどさまざまな形があります。
それぞれの特徴と活用シーンを理解することで、
自社に合った選択が可能になります。
この章では、各ツールのメリットとデメリットを解説します。
ドキュメント型
ドキュメント型は、
Microsoft WordやGoogleドキュメントのように、
自由に文章を書き込める汎用型のドキュメント作成ツールです。
- メリット
細かなレイアウト調整や画像挿入ができ、自由度が高い
- デメリット
情報の体系化や複数人での共同編集、検索性はやや弱く、
マニュアルの規模が大きくなると管理が難しくなる
社内Wiki
社内Wikiは情報をページ単位で管理し、
リンクで相互に関連付けることができるツールです。
- メリット
リアルタイムでの共同編集や更新履歴の管理が容易
- デメリット
編集ルールが曖昧だとページが乱立して情報が散乱しやすくなるため、
運用ルールの整備が不可欠
FAQツール
Q&A形式で情報を蓄積し、
検索性と再利用性に優れたツールです。
- メリット
質問をキーワード検索すると関連する回答が一覧表示されるため、
自己解決を促しやすい
- デメリット
個別のQ&Aに分かれているため、業務全体の流れや手順を俯瞰しづらい
ツール選定の考え方と注意点
マニュアル作成に最適なツールを選ぶ際には、
ツール単体の機能だけでなく、
組織の情報共有スタイルや利用者のITリテラシーにも配慮する必要があります。
例えば、
文章作成に慣れていない現場のメンバーが多い場合は、
FAQ形式の方が入力・更新のハードルが下がるかもしれません。
また、ツールを導入した後の運用フローや
メンテナンス体制まで見据えることで、
ツール選定の失敗を避けられます。
ドキュメント型・Wiki型・FAQツールにはそれぞれ特性があり、
目的や運用体制によって向き不向きがあります。
自社の課題や利用シーンに応じて、
最適なツールを選定・組み合わせて活用することが重要です。
次の章以降では、
マニュアル作成に向いているFAQツールについて解説します。
▼ こちらの記事もおすすめ ▼
業務効率化に向けた社内ツールの導入と定着させるためのポイントとは
FAQツールがマニュアルに“使える”理由とは?

近年注目されているFAQツールは、マニュアル整備にも有効です。
FAQツールは検索性や更新性に優れているため、
属人化防止にもつながります。
この章では、なぜFAQツールがマニュアルに適しているのか、
その理由を明らかにします。
検索性・再利用性に優れている
FAQツールは質問と回答をセットで登録するため、
キーワード検索に特化した作りになっています。
そのため、
大量の情報から必要な内容を素早く見つけられるので、
マニュアルとしての利便性が高まります。
さらに、回答単位で管理していくため、
一部の回答だけを更新したり、
複数のFAQに同じ回答をリンクさせることも容易です。
これにより、ひとつのFAQを別のFAQに利用したりと、
情報の再利用が可能になるため、
マニュアル作成に必要な時間が大幅に軽減されます。
自己解決を促進し、問い合わせ削減へ
FAQツールを導入すると、
社員や顧客が自分で疑問を解決しやすくなり、
社内ヘルプデスクやカスタマーサポートへの問い合わせが減少します。
問い合わせの多い質問を集中的にFAQ化することで、
よくある課題を先回りして解消できるため、
業務効率の改善につながります。
また、ユーザーは24時間いつでもアクセスできるため、
時間や場所に制約されず、疑問を解決することができます。
更新性が高く、属人化もしにくい
FAQツールは回答単位で編集・追加ができるため、
情報の更新がスピーディーに行えます。
属人化していたノウハウも
チームで共有・編集しやすくなり、
特定の担当者に依存しない体制を構築できます。
さらに、変更履歴や更新ログを管理できる機能がある場合、
「誰がいつどの情報を変えたか」を追跡可能です。
これにより、情報の信頼性や透明性も向上します。
▼ こちらの記事もおすすめ ▼
活用方法が幅広い
FAQツールは社内マニュアルだけでなく、
外部向けのカスタマーサポートや製品情報の整理にも活用されています。
部門ごとの手順書やナレッジ共有、
問い合わせ対応の履歴管理など、
多岐にわたる用途に対応できる柔軟性がFAQツールの魅力です。
FAQツール導入の際には、
どの部門でどのように活用したいかを明確にし、
社内全体の情報共有基盤として設計することで、
より大きな効果を得ることができます。
FAQツールを導入する前に整理すべきこと

FAQツールの効果を最大化するには、導入前の準備が重要です。
目的や業務範囲、運用体制の明確化が、
その後のFAQツールの活用度に直結します。
この章では、
FAQツール導入前に押さえておきたい具体的な準備項目について整理します。
マニュアル化したい業務を明確にする
FAQツールをマニュアル作成で効果的に活用するには、
まず「どの業務やどんな課題をマニュアル化するか」を明確にしましょう。
すべての業務を一度にマニュアル化しようとすると
範囲が広すぎて管理が難しくなります。
優先順位をつけ、
問い合わせが多い業務や属人化リスクの高い分野から
着手するのがおすすめです。
また、対象業務の業務フローや担当者の知見を整理し、
マニュアルに反映すべきポイントを洗い出すことも重要です。
閲覧者の課題や検索傾向を把握する
誰がどのような情報を求めているのかを把握することが、
FAQツールの運用成功に直結します。
例えば、社内での問い合わせ内容を分析したり、
検索ログを活用してどんなキーワードで調べられているかを把握すると、
必要なFAQ項目を効率よく作成できます。
閲覧者の視点を取り入れることで、
的外れな情報登録や無駄なコンテンツ作成を防ぎ、
満足度の高いマニュアル運用が実現します。
運用体制と更新ルールを事前に定めておく
FAQツールは、
導入後も継続的に情報を更新し続ける必要があります。
そのために、
担当者や責任者の役割分担、
更新頻度、承認プロセスを明確にしておくことが大切です。
また、運用ルールをマニュアル化し、
全員が理解・共有できる体制を整えましょう。
こうした事前準備がないと、情報が古くなったり、
内容がバラバラになって利用されなくなるリスクが高まります。
▼ こちらの記事もおすすめ ▼
FAQツール「ナレッジリング」でマニュアル作成がどう変わるか?

実際にFAQツールを活用する中で、
どのようにマニュアル作成に変化をもたらし、
効果を発揮するのでしょうか。
本章では、FAQツール「ナレッジリング」の機能や導入メリット、
具体的な活用シーンを通じて、その有用性を解説します。
Q&A形式で直感的な情報整理ができる
「ナレッジリング」は、
Q&A形式に特化したFAQツールで、直感的な操作性が特長です。
業務の疑問や課題を「質問」として登録し、
それに対する「回答」を整理することで、
現場のリアルな声を反映したマニュアルが簡単に作成できます。
また、カテゴリ分けやタグ付けも可能で、
情報が体系的に整理されるため、
誰でも迷わず目的の情報にたどり着けます。
ユーザーがどのFAQを閲覧しているかを確認できる
ナレッジリングには、
どのFAQがよく閲覧されているか、
どんなキーワードで検索されているかを分析できるアクセス解析機能があります。
これにより、現場のニーズや課題をリアルタイムで把握でき、
マニュアルの改善点や追加すべきFAQ項目を的確に見極められます。
利用状況を可視化することで、運用者も改善意欲が高まり、
PDCAサイクルを回しやすくなります。
ナレッジリングの導入事例と活用シーンの紹介
ナレッジリングは、
製造業の現場教育やカスタマーサポートの問い合わせ対応、
社内ヘルプデスクの業務効率化など、
多様なシーンで活用されています。
ある製造業では、ベテラン社員のノウハウをQ&A形式で蓄積し、
新人研修の質が向上しました。
また、IT企業のサポート部門では、
問い合わせ内容をFAQ化することで
問い合わせ件数を30%削減した事例もあります。
このように、
ナレッジリングはマニュアル作成と運用を効率化できるため、
さまざまな企業や職種にとって、
知識共有を加速させる強力なツールになるのです。
▼ 他社の成功事例を見てみる ▼
まとめ
マニュアル作成がうまくいかない理由には、
情報の属人化や作成負担の大きさ、完成後の活用不足が挙げられます。
しかし、目的を明確にし、
テンプレートや運用ルールを整備しながらPDCAを回すことで、
継続的かつ効果的なマニュアル運用は可能です。
さらに、FAQツールを活用すれば、
質問と回答の形式で情報を整理しやすく、検索性や更新性も大幅に向上します。
特に「ナレッジリング」は直感的な操作性とアクセス解析機能を備えているため、
業務の属人化解消や問い合わせ削減に貢献します。
マニュアルを単なるドキュメントではなく、
組織の知識基盤として活用することで、
業務効率化と社員のスキルアップを同時に実現しましょう。