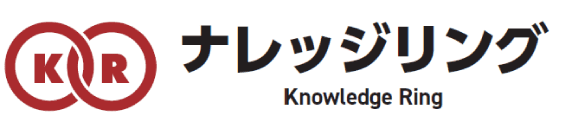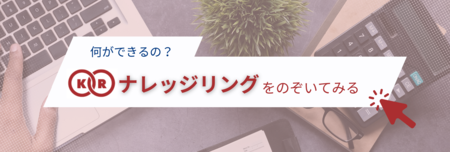ナレッジベースとは?構築のメリットとツールとしての活用アイデアをご紹介

こんにちは。
ナレッジリングのマーケティング担当の谷知です。
ナレッジベースとは、
特定の分野やテーマに関する情報や知識を体系的にまとめた仕組みのことです。
ナレッジベースを活用することで、
対応の迅速化や業務効率の向上が期待できます。
本記事では、
ナレッジベースの概要と重要性、
さらにナレッジベースを実際に活用する際のアイデアや
構築時のポイントを詳しく解説します。
- 直感的なデザインで誰でもカンタンに操作できる!
- 業界最安クラスだから導入しやすい!
- 導入後もサポート付きで安心!
機能の特徴や導入事例をご紹介しております。無料プランやデモもご用意しておりますので、ぜひご覧ください。
ナレッジベースとは?その概要と重要性

ナレッジベースの定義と目的
ナレッジベースとは、
業務で得られる知識や経験を整理し、
一元的に管理・活用できるようにした仕組みのことです。
ナレッジベースを活用する主な目的は、
情報を迅速に検索・共有することや、
業務効率の向上、さらに企業内での知識の属人化を防ぐことにあります。
また、ナレッジベースの活用方法は多岐にわたり、
FAQや業務マニュアルから、顧客対応のサポート資料、
さらには企画立案に必要な情報整理等、
様々な場面での活用が期待できます。
ナレッジベースが注目される背景とは
近年、ビジネス環境の急速な変化や人材の流動化が進む中で、
組織内での知識共有の重要性がますます高まっています。
これに加え、クラウドサービスの普及により、
場所を問わずナレッジを活用できる環境が整備されたことも、
ナレッジベースの活用を後押しする要因となっています。
さらに、
ナレッジベースの構築によって業務効率が向上することで、
企業の競争力を強化することが可能になる点も注目を集める理由の一つです。
企業や組織におけるナレッジベース活用場面
ナレッジベースは、
さまざまな場面で有効活用されています。
例えば、社内FAQとしてナレッジベースを活用することにより
従業員が抱える疑問を迅速に解決できるほか、
プロジェクト管理において進捗状況や共有資料を一元化し、
チーム全体の効率を高めることが可能です。
また、新人教育のために研修資料を整理・統合することや、
顧客対応での過去の問い合わせ履歴や解決方法を蓄積することで、
顧客満足度を向上させるケースもあります。
ナレッジベースは、
こうした多様な業務プロセスを支える強力なツールとして機能します。
SECIモデルやナレッジマネジメントとの関係
ナレッジベースは、
組織内の知識を「形式知」として整理・蓄積し、
それを効果的に活用するための土台として機能します。
このプロセスは、
「暗黙知」と「形式知」の相互変換を示したSECIモデルと深い関係があります。
例えば、暗黙知を表現化することで形式知に変換し、
それをナレッジベースに蓄積することで、
多くの人と知識共有ができます。
このようなサイクルを繰り返すことで、組織全体の知的資産を高め、
生産性の向上や業務改善、
さらに社員ひとりひとりの成長を後押しすることが可能です。
▼ こちらの記事もおすすめ ▼
ナレッジベースを活用する5つのメリット

メリット①業務効率化と時間短縮
企業としてナレッジベースを活用することで、
業務の効率化と時間の短縮が実現可能です。
例えば、社員が必要な情報を検索しやすくなったり、
繰り返される質問や業務マニュアルを一元化したりすることで、
無駄な作業が削減できます。
また、ナレッジベースを社内で浸透させると、
日々の業務プロセスがスムーズになります。
さらに、ナレッジベース向けのツールも活用すると、
情報の更新や検索性が向上し、さらに生産性を高めることができます。
メリット②属人化の防止と知識の継承
ナレッジが一部の社員に集中すると、
その社員が退職時や異動した時に、
ナレッジが共有されていないことが原因で、
業務が滞ってしまうという問題が発生します。
日頃からナレッジベースを構築し、
企業の知識を誰でも利用できる形で共有しておくことで、
業務の属人化を防ぐことが可能です。
さらにナレッジマネジメントを実践すれば、
企業内の暗黙知を形式知へ変換するプロセスを確立でき、
組織全体でのスムーズな知識の継承が期待できます。
▼ こちらの記事もおすすめ ▼
メリット③社員満足度の向上とストレス軽減
業務内で必要な情報を得られない場合、
社員がストレスを抱えてしまう可能性があります。
しかし、ナレッジベースを活用して情報が一元化されると、
どこからでも素早く必要な知識を得られるため、
社員のストレス軽減にもつながります。
また、ナレッジベース向けのツールも活用すると、
社員が自発的に知識や情報を得ることができるため、
社員の満足度も向上するでしょう。
メリット④対応品質の向上による顧客満足度向上
ナレッジベースは、
顧客対応の品質向上にも大きく寄与します。
顧客対応時に必要な情報を得たい時に、
ナレッジベースがあれば、
迅速かつ一貫した情報を見つけることができるので、
カスタマーサポートの効率が上がり、
顧客満足度の向上に繋がります。
メリット⑤データ分析や知見蓄積で戦略を立てられる
ナレッジベースで集積されたデータを分析することで、
企業戦略の立案に役立てることが可能です。
どの情報が最も検索されているのか、
閲覧頻度や「いいね」の多いコンテンツなどを把握することで、
閲覧している人が求めているナレッジをズレなく確認することができます。
分析機能をうまく活用することは、
市場動向や組織内のニーズを把握し、
より効果的な経営戦略の構築にもつながります。
ナレッジベース構築の成功ポイントと注意点

目的やゴールを明確にする
ナレッジベースを活用する際、
まずはその利用目的やゴールを明確にすることが重要です。
例えば、
「社内FAQとして業務の効率を上げる」「顧客対応の質を向上させる」など、
具体的な課題をもとに活用計画を立てることが成功への第一歩です。
また、どのような人に活用してもらいたいか、
そして利用するシチュエーションを具体化することも不可欠です。
自社に合った適切なツールを選択する
ナレッジベースを効果的に運用するには、
適切なツールを選ぶことが欠かせません。
検索性や使いやすさ、
さらに既存の業務ツールとの連携が可能かどうかを重視しましょう。
クラウド型のツールであれば、
社内外問わずどこからでもアクセス可能なため、利便性も高まります。
また、導入段階では、
まずは小規模に導入し、試験運用を行い、
本格導入の前にツールの有用性を確認することをおすすめします。
そうすることで、
不必要なコストやリスクを抑えることができるからです。
蓄積されているナレッジの整理
ナレッジベースを活用する際は、
蓄積されているナレッジを整理してから仕組化することが必要です。
ナレッジを整理することで、
ナレッジの不必要な重複や不整合を防ぎ、
閲覧者が必要な情報を迅速に見つけられる仕組みを構築することができます。
ナレッジを整理していく際には、
頻繁に検索されるキーワードや業務プロセスを意識して、
階層的な構造やタグ付けを活用すると良いでしょう。
また、ナレッジの量が膨大になった場合、
スムーズに管理できる体制を整えていくため、
メンテナンス方法も明確にしておく必要があります。
▼ こちらの記事もおすすめ ▼
ツール導入後の運用管理と継続的な改善
ナレッジベースを成功へと導くためには、
ツール導入後の運用管理が非常に重要です。
ナレッジを定期的に更新・追加する仕組みを設け、
情報が常に最新である状態を保っておきましょう。
さらに、利用状況を分析し、閲覧者が不足だと感じている情報は何か、
高頻度で検索されている項目は何かといった分析データを活用して
システムを改善していくことも大切です。
ナレッジベース活用の失敗防止策
ナレッジベース活用の失敗を防ぐためには、
いくつかのポイントを押さえておく必要があります。
例えば、目的が曖昧なまま活用を進めてしまうと、
企業内での活用が定着せず成果が得られません。
また、情報が多すぎて検索性が悪化するケースや、
更新が滞って古い情報が残ることもよくある失敗です。
実例として、ある企業では、
全員が日次で更新を行うルールを作ることで、
ナレッジベースを常に最新化し業務効率を向上させました。
このように、活用開始後も継続的な運用と改善を意識して取り組むことが大切です。
【おすすめ5選】ナレッジベース活用アイデア

1. 社内FAQとしての活用
ナレッジベースの仕組みを活かして、
社員から頻出する質問や課題に対する回答をまとめた
「社内FAQ」としてナレッジベースを活用する方法があります。
例えば、福利厚生や就業規則、
パソコンの操作方法といった日常的に必要な情報を
ナレッジベースを活用して一元管理することで、
社員からの問い合わせ対応時間を大幅に削減できます。
また、クラウドツールとともにナレッジベースを活用すれば、
リモートワーク中の社員も簡単に情報を検索し参照できるため、
働く場所に関係なく業務をスムーズに進めることもできます。
▼ こちらの記事もおすすめ ▼
2. プロジェクト管理での情報共有ツール
ナレッジベースは、
プロジェクト管理においても情報共有の強力なツールとして活躍します。
プロジェクトに紐づいた資料や進捗状況、
タスクの詳細をナレッジベース上に整理しておくことで、
関係者間で効率的に情報を共有できます。
特に、異なる部署や複数のメンバーが関わるプロジェクトの場合、
情報の透明性が高まり、業務の属人化を防ぐことが可能です。
また、ナレッジ履歴を蓄積することで、
似たようなプロジェクトが発生した際に過去のナレッジを再利用できるので、
時間短縮にも繋がります。
3. 研修や教育コンテンツの一元管理
社内での研修や新人教育の際にも、
ナレッジベースは大きな効果を発揮します。
例えば、マニュアルや動画、
ケーススタディなどの教育コンテンツを一元管理することで、
新入社員やキャリアチェンジした社員が
必要な資料へ即座にアクセスできるようになります。
これにより、教育期間を短縮できるだけでなく、
統一感のある研修を実施することができます。
また、教育ツールとして利用する際には、
関連資料をリンクさせるような仕組みを用意することで、
社員がスムーズに研修を受けることが可能です。
4. 問い合わせ対応の効率化とサポート向上
問い合わせ対応においても、
ナレッジベースを活用することは非常に効果的です。
よくある質問や課題についての回答を集めた顧客向けFAQを公開することで、
顧客の自己解決を促進でき、
問い合わせ対応の工数を削減することができます。
また、社内サポートチームも顧客向けFAQを活用することで、
迅速かつ的確な対応が可能となり、
結果的に顧客満足度の向上に繋がります。
さらに、ナレッジベースを活用するためのツールには
「最も検索される質問」や「閲覧数ランキング」といった分析機能が備わっているので、
新たな課題の発見やサービス改善のヒントにもなります。
5. ナレッジ活用による提案力の向上
ナレッジベースは、
営業の際の提案力を高めるためのサポートにもなります。
例えば、過去の提案資料や顧客ヒアリングの結果、
成功事例などをナレッジベースに蓄積することで、
営業担当者が必要な情報を活用できるようになります。
これにより、
顧客のニーズに合った的確な提案を短時間で行えるため、
競合他社との差別化にも繋がります。
また、ナレッジベースで蓄積された情報をもとにデータ分析を行うことで、
顧客に対するより戦略的なアプローチを考案することも可能です。
ナレッジベースの活用にもおすすめのFAQシステム「ナレッジリング」のご紹介

最後に、おすすめのFAQシステム「ナレッジリング」をご紹介しましょう。
「ナレッジリング」は、いつでも・どこでも・カンタンな操作で社内の情報共有を促進し、
効率的に業務を遂行するための機能や特徴を備えたFAQシステムです。
【ナレッジリングで実現できること】
① 社員の自己解決力アップ
② 最新情報のタイムリーな共有
③ 業務効率の向上
ナレッジベースの活用にも役立つナレッジリングの機能を一部ご紹介します。
-
【おすすめ機能①】テキスト・ファイル・画像など、さまざまな形式による情報登録
ナレッジリングは、テキスト形式によるFAQの作成、
Word,Excel,PowerPoint,PDFなどのファイル形式によるマニュアル、
画像や動画の添付なども可能です。
どのような社員にも理解してもらいやすい形式を選択することができるため、
社員の自己解決力アップにつながります。

<キーワード検索ボックス>
-
【おすすめ機能②】検索されているキーワードの分析
ナレッジリングに登録されている情報を、利用者がどのようなキーワードで
検索しているか把握できる「キーワード分析」機能があります。
実際に検索で使用されているキーワードから、利用者が求める情報が何かを分析し、
新しい情報を追加したり既存の情報を更新したりすることで、
最新情報のタイムリーな共有が可能となります。

<キーワード分析>
-
【おすすめ機能③】テキストとファイルの同時検索
一度のキーワード検索で、テキストとファイルを同時に検索します。
また、ファイル内のテキストまで検索するため、ファイルのタイトルが分からなくても
キーワードに関連する情報が見つかりやすいことが特徴です。
探している情報に見つかりやすいため、
社員の業務効率向上を実現できます。

<FAQのテキストとファイル内テキストを同時検索している例>
まとめ
ナレッジベースとは、
企業や組織のナレッジを蓄積し、
必要なときにナレッジを迅速に活用するための大変便利な仕組みです。
ナレッジベースを活用することにより、
業務効率の向上や情報共有の促進だけでなく、
顧客満足度や従業員の満足度向上といった多くのメリットが得られます。
ナレッジベースを活用する際は、
組織の目的に合ったツール選定や運用計画を入念に設計すること、
そして、情報を整理しやすい環境や継続的な改善を行うことで
長期的にナレッジベースを活用していくことができます。
これからのビジネス環境では、
ナレッジベースを活用したナレッジマネジメントがますます重要になるでしょう。
ぜひ、この機会にナレッジベースの構築を検討してみてはいかがでしょうか。