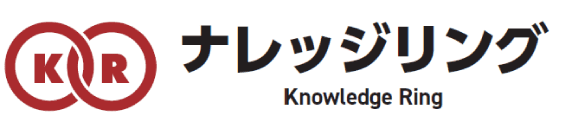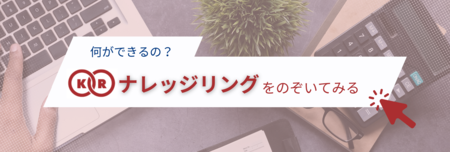なぜ社内Wikiは使われないのか?
解決策にFAQシステムを選ぶべき理由とは

こんにちは。
ナレッジリングのマーケティング担当の谷知です。
せっかく導入した社内Wikiが、いつの間にか誰にも使われなくなってしまう──。
そんな悩みを抱える企業は少なくありません。
「情報共有の基盤になるはずだったのに」
「結局メールや口頭でやり取りしている」など、
社内Wikiの運用に限界を感じていませんか?
その原因は、コンテンツの質や更新頻度だけでなく、
「仕組みそのもの」にあるかもしれません。
本記事では、社内Wikiがうまく機能しない理由を明らかにし、
その解決策として注目される「FAQシステム」の情報共有手法と、
その運用に適したツール「ナレッジリング」をご紹介します。
クラウド型FAQシステム「ナレッジリング」がおすすめ!
- 直感的なデザインで誰でもカンタンに操作できる!
- 業界最安クラスだから導入しやすい!
- 導入後もサポート付きで安心!
機能の特徴や導入事例をご紹介しております。無料プランやデモもご用意しておりますので、ぜひご覧ください。
なぜ社内Wikiはうまく機能しないのか

社内Wikiを導入したにもかかわらず、
社内で活用されないという課題は多くの企業が直面しています。
原因は社内Wiki自体の性能ではなく、
情報の探しにくさや書き方の自由度の高さによる“運用のズレ”にあります。
よく挙げられる3つの課題を詳しく見ていきましょう。
課題①情報が蓄積されても「探せない」
社内Wikiでは情報が日々蓄積されていきますが、
それが「探せない」「見つからない」状態になってしまうケースが
非常に多く見られます。
カテゴリ分けやページ構成が属人的であったり、
検索機能が十分でなかったりすると、
必要な情報にたどり着くのに時間がかかり、
結果的に使われなくなってしまうのです。
また、タイトルが抽象的で内容との関連性が薄い場合も、
検索性が低下する一因となります。
情報が“あるのに使われない”という状態は、
業務効率を大きく損ね、社員の自己解決力も下げてしまいます。
こうした「情報迷子」を防ぐには、
構造的に“見つけやすくする仕組み”を選ぶことが求められます。
課題②「とりあえず書く」文化で読み手が不在に
社内Wikiは誰でも自由に書けるという利点がありますが、
それが裏目に出ると「とりあえず書いた情報」が乱立してしまう結果になります。
情報の書き手が読み手の視点を欠いたまま内容をまとめてしまうと、
文章が冗長になったり、必要な情報が埋もれてしまったりして、
結果的に読みにくくなります。
また、個人の表現方法や用語に依存しすぎると、
読み手が内容を正しく理解できず、
再検索する手間が発生することもあるでしょう。
このように、
書くことが目的化してしまうと、「活用されるナレッジ」にはなりません。
情報共有の本質は“伝わること”です。
そのためには、形式や書き方の統一と、
読み手視点の運用ルールを定めることが重要です。
課題③管理・更新が手間になり、放置されがちに
社内Wikiは一度作ったら終わりではなく、
継続的なメンテナンスが欠かせません。
しかし、誰がどの情報を更新するか、
どれが古くなっているのかを把握するのは容易ではなく、
更新の優先順位も曖昧になりがちです。
その結果、「放置された古い情報」が蓄積してしまい、
社員の信頼を失うことになります。
さらに、情報が多ければ多いほど更新のハードルが上がり、
次第に誰も手を付けなくなる悪循環に陥ります。
維持・更新の手間を最小限にし、
運用ルールをシンプルに保てるツールを選ぶことが必要です。
▼ こちらの記事もおすすめ ▼
社内Wikiの失敗しない作り方とは? 成功のポイントと運用のコツを徹底解説!
「情報共有の仕組み」を見直す重要性

社内Wikiが使われない背景には、
「情報の探しにくさ」や「使いやすい構造になっていない」など、
仕組み側の問題があります。
情報があることよりも、
必要な人に必要な情報が届くことが重要です。
ここでは、
情報共有を活性化するために見直すべき3つの視点を紹介します。
✓情報は“見つかる構造”にして初めて価値が出る
どれだけ良質な情報を掲載していても、
それが「見つからない」状態では意味がありません。
実際、社内Wikiの失敗原因の多くは
「検索性の低さ」や「構造の複雑さ」にあります。
例えば、カテゴリの分け方が曖昧だったり、
似たような情報が重複していたりすると、
社員はどれを見ればよいのかわからなくなります。
また、検索機能が弱いと、必要な情報にたどり着けず、
「結局人に聞く」という行動に戻ってしまいます。
情報共有を活性化するには、
「情報を探すストレス」を極力なくすことが大切です。
FAQシステムのように、
質問形式で情報が整理されていると、
検索性が高まり、社員が情報を見つけやすくなります。
▼ こちらの記事もおすすめ ▼
✓「誰が何を知りたいか」から逆算する設計へ
情報共有の仕組みを設計する際、
やりがちなのが「書きたい人が書きたいことを書く」スタイルです。
しかしそれでは、
社員が知りたいことにアクセスしづらい構成になってしまいます。
大切なのは、
「誰が・いつ・どんなシーンで・何を知りたいのか」を想定し、
そのニーズから逆算して情報を設計することです。
例えば、業務マニュアルひとつとっても、
「新入社員が入社初日に使うか」
「ベテラン社員が例外対応で調べるか」で、
求める内容や表現は異なります。
FAQシステムでは「よくある質問」形式でニーズを明確化しやすく、
社員視点の構造が自然に生まれます。
設計の主導権を“作る側”ではなく“使う側”に移すことが、
活用される社内Wikiを作る第一歩です。
✓「使われ続ける仕組み」こそが成功の鍵
一度は整備された社内Wikiでも、
更新されなくなるとすぐに形骸化します。
重要なのは「一度作って終わり」ではなく、
「継続的に使われる」仕組みを作ることです。
情報が古くなると信頼性が下がり、誰も参照しなくなり、
結果として誰も更新しないという悪循環が始まります。
この悪循環を断ち切るには、
「運用ルール」と「責任分担」、
そして「更新のしやすさ」がポイントになります。
FAQシステムでは、質問単位での編集・追加がしやすく、
全体の情報構造に影響を与えにくいため、
現場が気軽に更新しやすいというメリットがあります。
使われるから更新され、更新されるからまた使われる——
この好循環を生む設計こそが、
情報共有の仕組みに求められる成功ポイントなのです。
社内WikiとFAQシステムの違いとは?

社内WikiとFAQシステムは、
どちらも情報を蓄積・共有するためのツールですが、
構造や目的が大きく異なります。
それぞれの違いを整理します。
目的の違い──蓄積と解決
社内WikiとFAQシステムの違いのひとつとして、
「目的」が挙げられます。
- 社内Wikiの目的
業務マニュアルや手順書、ナレッジを自由に記録し、社内に蓄積すること
- FAQシステムの目的
「よくある質問に対する答え」を効率的に提供し、
ユーザー(社員)が自己解決できるようにすること
社内Wikiは全体像を俯瞰するのに向いていますが、
欲しい情報をピンポイントで得るには不向きな場合があります。
一方でFAQシステムは、
社員からの質問を想定して構成していくため、
社員が必要な答えに最短でたどり着くことが可能です。
この社内WikiとFAQシステムの目的の違いが、
日常的に活用される際に選ばれるかどうかの差を生むのです。
構造の違い──階層型と質問応答型
社内Wikiは階層的にページを作成・リンクしていく構造のため、
整理されていないと迷路のようになりがちです。
社員は複数のページを行き来しながら情報を探す必要があり、
目的の情報にたどり着くのに時間がかかります。
対してFAQシステムは、
1つの質問に対して1つの回答が結びついたフラットな構造です。
これにより、社員はページを横断することなく、
短時間で正確な答えを得られます。
情報を見つけるまでの速さと手間が、
社内WikiやFAQシステムの活用度を大きく左右するのです。
運用スタイルの違い──自由記述と管理型
社内Wikiは誰でも自由に
ページを追加・編集できる柔軟性が魅力ですが、
それゆえにルールが曖昧だと内容が乱雑になりやすいという欠点もあります。
FAQシステムは質問と答えを一対で登録し、
管理者が編集や更新を一元的に行うため、
情報の品質が保たれやすい仕組みです。
また、FAQシステムは
「解決済みの情報」だけを整理して掲載するため、
古い情報や曖昧な記述を削除しやすく、
常に最新・正確な情報を保つ運用が可能です。
▼ こちらの記事もおすすめ ▼
社内WikiにFAQシステムが「選ばれる」理由

FAQシステムは、
必要な情報をすぐに見つけられる“ユーザー視点の設計”を心がけることで、
社内でも活用率が高いツールのひとつです。
社内WikiとしてFAQシステムが選ばれる理由を解説します。
ユーザー視点で設計された情報構造
FAQシステムは、
社員が抱える具体的な疑問を出発点に情報を整理するため、
ユーザー視点での利便性が高いのが特長です。
必要な答えが明確に分類・表示されるため、
情報を探す手間が大幅に削減されます。
従来のWikiでは
「どのページに答えがあるか」を探す手間が発生しますが、
FAQでは検索キーワードやカテゴリーにより一瞬で答えを表示できるため、
社員の操作性が向上します。
日常的に「すぐ見つかる」という機会を増やすことで、
社員の利用率が自然に高まっていきます。
質問単位で探せる・答えられる
FAQは「1つの質問と1つの答え」がセットになっており、
情報が均一でわかりやすいというメリットがあります。
例えば、業務でよくある「パスワードの再発行方法」や
「申請書のフォーマット場所」など、
具体的な課題に対してピンポイントで答えを用意することができます。
社員は目的の情報を即座に取得できるため、
社内ヘルプデスクや担当者に同じ質問を繰り返す回数が減り、
社員の自己解決力が向上します。
運用ルールが明確で、更新しやすい
FAQシステムは、
コンテンツの登録や更新のフォーマットが明確なため、
誰が更新しても情報の品質が均一に保たれます。
さらに、「解決済みの情報だけを残す」という仕組みがあるため、
古い情報や重複情報が自然に整理されます。
運用担当者にとっても
「どの質問が閲覧されているか」
「どれが不要か」
といったデータが可視化され、
改善サイクルを回しやすくなる点も大きな強みです。
▼ こちらの記事もおすすめ ▼
社内WikiにFAQシステムを取り入れるという選択肢

もし、すでに社内Wikiを導入していて運営に迷いがある場合、
FAQシステムを補完的に取り入れることで、
情報が整理され、活用しやすい構造に生まれ変わります。
ここでは、社内WikiとFAQシステムを組み合わせるメリットを解説します。
「書き溜める」から「答える」への発想転換
社内Wikiは多くの場合、
情報を大量に「書き溜める」方向で運用されます。
しかし、社員が求めているのは「業務課題の解決」です。
FAQシステムを導入すると、
必要な情報を「質問と答え」に変換し、
課題解決をゴールとした情報整理が可能になります。
この流れによって、社内Wiki内の情報も見直され、
「使える情報」だけを効率的に残すきっかけにつながります。
現状のWikiをベースにFAQを補完する
すでに存在する社内Wikiを活かしながら、
よくある質問や業務ナレッジを
FAQのひとつとして抜き出す方法が有効です。
FAQのページをWikiの入り口に配置することで、
社員はまずFAQから解決策を探し、
それでも見つからない場合にWikiを参照する、
という自然な導線を構築できます。
この組み合わせにより、
Wikiの情報が“活用される”状態へと改善されます。
「使われる情報」への第一歩としてのFAQシステムを選ぶ
FAQシステムは、情報整理の第一歩として最適です。
よく参照される内容をFAQとして整理することで、
必要な情報がすぐに見つかる状態を実現できます。
これにより、
社員は「FAQの中に答えがある」という期待を持ち、
利用が促進されます。
結果的に、Wikiに眠っていた情報も再利用され、
社内ナレッジの循環が活性化します。
▼ こちらの記事もおすすめ ▼
社内Wikiに「ナレッジリング」が選ばれる理由

社内WikiにFAQシステムの運用を考えるなら、
社内利用に特化したFAQシステム「ナレッジリング」が有力な選択肢です。
シンプルで使いやすく、
既存のWikiとも併用できる柔軟な仕組みが、
社内情報共有の課題解決に役立ちます。
FAQ構造+社内運用に特化したシステム
ナレッジリングは、
社員が求める答えをスピーディーに見つけられるよう、
シンプルで直感的な設計を追求しています。
FAQの登録・検索・更新が容易で、
他業務にも支障が出にくい作りになっています。
複雑なマニュアルなしでもすぐに運用を開始できる点は、
多忙な企業担当者にとって大きなメリットです。
変化に強い設計で、成長する組織にフィット
ナレッジリングは、
社内の変化や成長に柔軟に対応できる設計が特長です。
部署の新設や業務フローの変更など、組織は常に進化していきます。
その中で情報共有の仕組みも、
柔軟にアップデートできることが求められます。
ナレッジリングはカテゴリやタグ設計の見直し、
FAQの並び替え、アクセス権の設定変更などが簡単に行えるため、
社内のニーズに合わせて常に最適な状態を保つことができます。
また、運用中に
「使いにくい」「見つけづらい」といった課題が出てきた場合でも、
社内で完結できる編集性の高さも魅力です。
変化に強く、持続可能なナレッジ基盤を求める組織にとって、
ナレッジリングは頼れるシステムとなるでしょう。
社内Wiki運用に向いている3つの理由
ナレッジリングが社内Wikiの運用に向いている理由として
主に3つ挙げられます。
- 柔軟な権限管理が可能
部署単位で閲覧・編集範囲をコントロールすることができ、
情報漏洩のリスクを抑えつつ必要な人に必要な情報だけを届けることができます
- Q&A形式により情報の検索性・再利用性が高い
1トピック1情報の構造で整理されているため、
キーワード検索やカテゴリ別の閲覧がしやすく、過去のナレッジを簡単に活用できます
- 自己解決率を高める仕組みが整っている
必要な情報にすぐアクセスできることで、
社内ヘルプデスクなどへの問い合わせを減らし、業務効率の向上につながります
以上のことから、
社内Wikiの課題を補完しつつ、
ナレッジリングでFAQシステムとして運用ができるため、
業務の効率化が期待できます。
▼ 他社の成功事例を見てみる ▼
まとめ
社内Wikiが使われない原因は、
情報の探しにくさや更新不足など、仕組みそのものにあることが多いです。
FAQシステムを取り入れることで、
必要な情報を効率よく届け、社員の自己解決を促進できます。
特に「ナレッジリング」は、
社内Wikiと相性が良く、運用をシンプルかつ効果的に改善します。
社内情報共有の停滞を感じているなら、
FAQシステムへの移行は有力な選択肢になります。
社内Wikiに限界を感じている場合は、
FAQシステムの追加運用を検討してみてはいかがでしょうか。