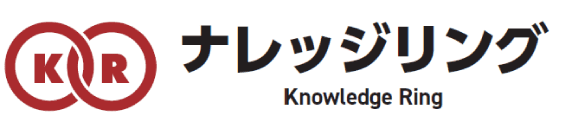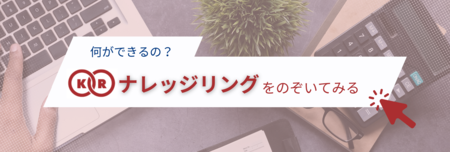社内ヘルプデスクとは?
「聞かれる前に答える」仕組みで業務効率アップ!

こんにちは。
ナレッジリングのマーケティング担当の谷知です。
社内で日々発生する
「PCが動かない」「システムにログインできない」
といった問い合わせに対応する担当者の負担が増える中、
「社内ヘルプデスク」という仕組みに注目が集まっています。
しかし、社内ヘルプデスクについて
「何をするのか」「どんな役割があるのか」など、
明確に定義されていないケースも多く、
効率化に踏み切れない企業も少なくありません。
この記事では、社内ヘルプデスクの仕事内容や課題、
業務効率化の方法、ツール導入のステップ、
そして社内ヘルプデスク導入の際におすすめのFAQツール
「ナレッジリング」について解説します。
- 直感的なデザインで誰でもカンタンに操作できる!
- 業界最安クラスだから導入しやすい!
- 導入後もサポート付きで安心!
機能の特徴や導入事例をご紹介しております。無料プランやデモもご用意しておりますので、ぜひご覧ください。
社内ヘルプデスクとは何か?

まず、社内ヘルプデスクとは企業内でどのような役割を担っているのか、
業務内容や他部門との違いを解説していきます。
社内ヘルプデスクの基本的な役割とは
社内ヘルプデスクの役割は、
社内の問い合わせ対応を通じて、
業務を円滑に進めるためのサポートを行うことです。
具体的な対応例は以下です。
- パソコンやプリンターの不具合発生時の対応
- 業務システムの操作方法の案内
- ソフトウェアのインストール方法の案内
社内ヘルプデスクでは、
このような社内で起きるさまざまな「困った」に対応します。
また、対応内容を記録し、
トラブルの傾向を把握して再発防止策を講じることも重要な業務です。
社内ヘルプデスクでは、対応スピードや正確性が求められる一方で、
問い合わせが集中する時期には、対応に時間がかかってしまうため、
業務負荷が高まりがちです。
▼ こちらの記事もおすすめ ▼
社内ヘルプデスクの仕事内容って?
社内ヘルプデスクの仕事内容は多岐にわたりますが、
代表的な業務には
「IT機器のトラブル対応」
「業務アカウントの再発行」
「社内システムの操作案内」
「FAQやマニュアル作成」などがあります。
特にIT部門に属する場合は、
パソコン機器やネットワークのトラブル対応など
専門的な知識も求められることがあります。
最近では、チャットツールを通じて対応するケースも増えていますが、
情報が散在しやすく、
対応履歴の蓄積や可視化に課題を感じている企業も多いのが実情です。
他部門との違い
社内ヘルプデスクは、
情報システム部門や総務部門、カスタマーサポート部門などと混同されがちですが、
対応する「対象」が異なります。
情報システム部門はシステムやインフラの構築・運用が中心、
総務部門は社内手続き全般、カスタマーサポート部門は顧客対応が中心です。
一方、社内ヘルプデスクは「社内ユーザーへの問い合わせ対応」が主軸となります。
職域が重なる部分も多いため、
役割分担が曖昧だと対応の重複や抜け漏れが発生しやすくなります。
そのため、業務領域を整理し、
専用窓口としての仕組みを整えることが求められます。
社内ヘルプデスクの課題とは?

社内ヘルプデスクは、
日々の問い合わせに迅速・的確に対応する重要な役割を担いますが、
運用面では多くの課題を抱えています。
社内ヘルプデスクがよく抱える課題を3つ挙げていきます。
業務上の悩み(問い合わせ対応の属人化・対応漏れなど)
多くの企業で見られる課題の一つが「属人化」です。
問い合わせへの対応が個人の経験や記憶に頼っている場合、
その人が不在だと誰も対応できなくなるリスクがあります。
また、対応履歴を残していないと、
過去のやりとりが参照できず、
同じ質問に何度も時間を取られる原因にもなります。
さらに、複数方面からの問い合わせ(メール、チャット、電話)が混在すると、
対応漏れも起きやすくなります。
こうした課題は、工数の増大や社員のストレス、
最終的には業務の停滞につながりかねません。
非効率な対応がもたらすコストとリスク
非効率な問い合わせ対応は、
目に見えない「コスト」と「リスク」を生み出します。
例えば、1件の質問に毎回数分を費やす場合、
年間で見れば膨大な時間が消費されています。
これにより、本来集中すべき業務が圧迫され、生産性の低下を招きます。
また、対応ミスや伝達ミスが起こると、
社内業務に支障をきたすだけでなく、
信頼の損失や重大なトラブルにも発展しかねません。
こうした背景から、
問い合わせ対応の効率化は「コスト削減」「リスク管理」の観点でも非常に重要です。
担当者が疲弊する
社内ヘルプデスクの現場では、
「対応が終わらない」「本来の業務に手がつかない」といった声が多く聞かれます。
特に人員が限られる中小企業では、
ヘルプデスク業務が他業務と兼任されているケースもあり、
対応のたびに集中力が途切れたり、作業が後ろ倒しになったりすることもしばしばです。
また、「以前も答えたはずの質問にまた答える」といったループ業務に対して、
モチベーションの低下を訴える担当者も少なくありません。
こうした現場の疲弊は、
離職リスクやサービス品質の低下を招く要因になります。
▼ こちらの記事もおすすめ ▼
社内ヘルプデスクの業務を効率化する「3つの改善ポイント」

社内ヘルプデスクの業務を効率化するためには、
「よくある質問の整理」や「対応フローの標準化」などの工夫が必要です。
ここでは、具体的な改善ポイントと、
それを支えるツール活用の重要性について解説します。
改善ポイント①マニュアル・ナレッジ共有・FAQを活用する
効率化の第一歩は、「よくある質問」の整理です。
社内ヘルプデスクによく寄せられる問い合わせを分類・可視化し、
マニュアルやFAQとしてまとめておくことで、
同じ質問への対応時間を削減できます。
また、マニュアルを作るだけでなく、
部署を越えてナレッジを共有できる環境を整えることも重要です。
例えば、ナレッジベースや社内Wikiを活用して、
誰でも検索・参照できるようにすることで、
担当者以外でも対応できる状態をつくることが可能になります。
こうした仕組みが整えば、
問い合わせ対応が属人化せず、
業務全体の流れもスムーズになります。
改善ポイント②ツールを導入する
問い合わせ対応を効率化するうえで、ツールの導入は非常に効果的です。
特に「FAQツール」や「問い合わせ管理システム」を使えば、
対応履歴の蓄積や問い合わせの検索性が向上し、
業務の見える化・標準化が進みます。
社内ヘルプデスクで対応している問い合わせの管理を
Excelやメールベースで運用するには限界があり、
情報の抜け漏れや対応の遅延が起こりやすくなります。
一方で、専用ツールを使えば、
誰がどの問い合わせにどう対応したかがすぐに把握でき、
業務の属人化も防げます。
特に少人数でも回る体制を作りたい企業にとっては、
手間を減らす仕組みの導入は欠かせないポイントでしょう。
改善ポイント③社内FAQツールで問い合わせ対応を仕組み化する
社内FAQツールを活用することで、
問い合わせ対応を「人に頼る運用」から「仕組みによる対応」へと変えることができます。
例えば、社員が疑問に思った際にまずFAQページで検索するような文化を作ることで、
ヘルプデスクへの問い合わせ件数自体を減らすことが可能です。
特に、ナレッジが整備されていない企業では、
質問が属人的にさばかれており、対応ミスや時間のロスが頻発します。
社内FAQツールを導入すれば、情報が一元管理され、
誰でも簡単に回答を確認できるため、
全社的な業務効率化と担当者の負荷軽減を両立できます。
▼ こちらの記事もおすすめ ▼
社内ヘルプデスクの導入は何から始めればいい?導入ステップを解説

社内ヘルプデスクの仕組み化や効率化に取り組むにあたって、
「何から始めればいいのか分からない」という声は少なくありません。
まずは現状の課題を可視化し、
小さな改善から着手することが成功の鍵です。
ここでは、具体的な導入ステップを3段階に分けて紹介していきます。
STEP①業務の棚卸しと問い合わせを分類する
最初に行うべきなのは、
「どんな問い合わせが発生しているか」
「誰がどう対応しているか」を把握することです。
日々寄せられる問い合わせを1〜2週間程度記録してみると、
意外と同じ質問が繰り返されていることに気づくはずです。
次に、それらをカテゴリ別に分類し、
「自動化できるもの」
「マニュアル対応で済むもの」
「専門知識が必要なもの」に分けていきます。
このステップを丁寧に行うことで、
改善の優先順位が明確になり、次の対応がスムーズになります。
また、業務の属人化や対応のバラつきといった課題も自然と浮かび上がってきます。
STEP②FAQ化しやすい情報を洗い出す
STEP①で業務の棚卸しと問い合わせを分類し終えたら、
分類した問い合わせの中から、
「何度も同じような質問が来る」
「新人からよく聞かれる」といった、
定型化しやすいものを洗い出しましょう。
こうした繰り返される質問こそ、最初にFAQ化すべき対象です。
例えば、
「Wi-Fiの接続方法」
「勤怠システムの打刻エラー」などは、
簡単な手順書や一問一答形式でまとめるだけでも問い合わせ数が大きく減ります。
FAQ化する際は、
実際の質問文とそのまま近い表現で書くことがポイントです。
現場の言葉で書かれたFAQは検索されやすく、
社員にとっても使いやすいナレッジとなります。
STEP③ツールを選定する
FAQにする問い合わせが洗い出せたら、
ツールの選定を進めます。
ツールを導入する際は、
「自社にとって何が必要か」を見極めることが大切です。
見極めるポイント例としては以下です。
- FAQの検索性が高いか
- カテゴリー分けがしやすいか
- 運用がシンプルか
また、機能が多すぎて使いこなせないツールや、
導入負荷が高いものは逆効果です。
導入時は、小さくスタートし、
実際に使いながら改善していく方が社内での運用が定着しやすくなります。
そして、社内のどの部署でも簡単に使えるような操作性を備えたツールを選ぶことが
導入後も継続していくためのポイントです。
そこでおすすめしたいのが、次に紹介する「ナレッジリング」です。
▼ こちらの記事もおすすめ ▼
社内ヘルプデスクにおすすめ!クラウド型FAQツール「ナレッジリング」

社内ヘルプデスクの効率化を実現するには、
現場に合ったツールの導入が不可欠です。
特に、FAQや問い合わせ情報を一元管理できるツールを使うことで、
属人化の防止だけでなく、業務の質とスピードも大きく向上します。
なかでも注目されているのが、
クラウド型FAQツール「ナレッジリング」です。
ここでは、ナレッジリングの特徴や社内ヘルプデスクの利用に向いている理由、
ナレッジリングの導入した効果について紹介します。
ナレッジリングとは?
ナレッジリングは、
社内外のよくある質問を蓄積・整理し、
誰でも簡単に検索・閲覧できるクラウド型FAQツールです。
誰でも直感的に使える操作性と、
質問のカテゴリ化や
記事やファイル内のキーワードまで探し出せることにより、
情報の登録・検索・更新がスムーズに行えます。
ナレッジリングの大きな特徴は、
「誰でも迷わず使えること」と「導入のしやすさ」です。
専用のITスキルがなくても、現場主導で運用を始めることが可能で、
数人規模の企業から大企業まで幅広く活用されています。
ナレッジリングは、
社内ヘルプデスク業務の改善を考えている企業にとって、
最初の一歩に最適なツールと言えるでしょう。
ナレッジリングはなぜ社内ヘルプデスクに向いているのか
ナレッジリングが社内ヘルプデスクに適している最大の理由は、
「よくある質問」の仕組み化と共有が簡単に行える点です。
問い合わせ対応で発生しがちな、
「同じ質問への繰り返し対応」や「回答のばらつき」を防ぎ、
担当者以外でも対応できる体制を作ることができます。
特に属人化の解消や、
情報の見える化が必要な場面でその力を発揮します。
また、情報を更新するとリアルタイムに反映されるため、
常に最新の情報を社内に届けることができ、
ミスや対応漏れの予防にもつながります。
ナレッジリングは業務効率化の「仕組み」として非常に有効なツールです。
ナレッジリングを導入した効果
ナレッジリングを導入した企業では、
「問い合わせ対応時間が約30~50%削減された」
「担当者が他業務に集中できるようになった」など、
明確な改善効果が表れています。
特に、よくある質問をFAQとして整備したことで、
従業員が自ら検索し自己解決する割合が増え、
ヘルプデスクへの問い合わせ数自体が減少したという事例もあります。
また、誰がどの質問に対応したかが可視化されるため、
対応品質の管理や改善のPDCAにも役立ちます。
社内のナレッジ共有を「仕組み」として運用するうえで、
ナレッジリングは非常に心強いパートナーです。
▼ 他社の成功事例を見てみる ▼
まとめ
社内ヘルプデスクは、
社員の業務を支える重要な存在でありながら、
その役割や業務内容が曖昧なまま運用されていることも少なくありません。
まずは、
対応業務の可視化とよくある質問の整理から着手し、
FAQの整備やツールの導入によって
対応を「人依存」から「仕組み」へと変えていくことが重要です。
特に、情報共有を仕組み化できるFAQツール「ナレッジリング」は、
導入のしやすさと効果の高さから、
社内ヘルプデスクの運用改善に最適な選択肢です。
対応に追われる日々から脱却し、
社員も担当者もストレスなく働ける環境をつくるために、
まずはナレッジリングの導入を検討してみてはいかがでしょうか。