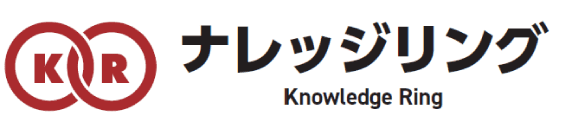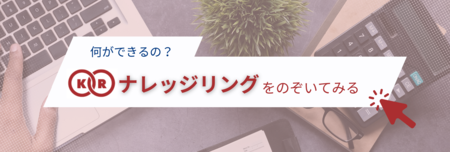社内ヘルプデスクを効率化する方法!課題解決と運用が変わる仕組みのポイント

こんにちは。
ナレッジリングのマーケティング担当の谷知です。
社内ヘルプデスクは、
従業員の疑問やトラブルを迅速に解消する
組織の“縁の下の力持ち”のような存在です。
しかし実際には、
「同じ質問が繰り返される」
「対応が属人化して疲弊する」
といった課題が多く、
運用の効率化に悩む担当者も少なくありません。
本記事では、
ヘルプデスク運用のよくある課題を整理し、
効率化によって改善を実現するための仕組みと成功のポイントを解説します。
クラウド型FAQツール「ナレッジリング」がおすすめ!
- 直感的なデザインで誰でもカンタンに操作できる!
- 業界最安クラスだから導入しやすい!
- 導入後もサポート付きで安心!
機能の特徴や導入事例をご紹介しております。無料プランやデモもご用意しておりますので、ぜひご覧ください。
社内ヘルプデスクとは?役割と重要性を再確認

まずは社内ヘルプデスクの役割を整理しておきましょう。
社内ヘルプデスクは単なる「問い合わせ対応部門」ではなく、
全社の生産性やナレッジ共有に直結する戦略的な存在です。
社内ヘルプデスクの役割について
社内ヘルプデスクは、
社員から寄せられるシステム、業務フロー、
勤怠、総務などに関する質問に対応し、
スムーズな業務遂行を支える部門です。
単に質問に答えるだけでなく、
業務知識の蓄積・共有を担う中核的な存在でもあります。
対応履歴を分析し、改善点を洗い出すことで、
組織全体の業務プロセスを見直すきっかけにもなります。
社内ヘルプデスクの質が組織全体の生産性を左右する
ヘルプデスクの対応品質は、
従業員の満足度や生産性に直結します。
例えば、
IT系企業では1件あたりの対応時間が平均10分短縮されるだけで、
年間数百時間の工数削減につながることもあります。
逆に、対応が遅れると
「聞いた方が早い」
「どうせ解決しない」
という風土が生まれ、
問い合わせが増える悪循環になってしまいます。
社内ヘルプデスクには、
質の高い対応を安定的に提供する仕組みづくりが不可欠です。
▼ 社内ヘルプデスクのさらに詳しい役割の説明はコチラ ▼
社内ヘルプデスクとは? 「聞かれる前に答える」仕組みで業務効率アップ!
社内ヘルプデスクの運用でよくある課題

社内ヘルプデスクがうまく機能しない原因の多くは、
運用上の構造的な課題にあります。
ここでは、現場でよく見られる3つの課題を整理します。
課題①同じ質問が繰り返される“ナレッジ共有不足”
多くの現場で見られるのが、
「前にも聞かれた内容への対応が減らない」ことです。
この原因は、
回答内容がナレッジとして整理・共有されていないことにあります。
社内ヘルプデスクの担当者間で情報が散在していると、
質問が繰り返され、対応コストが増加し、
結果として、社内ヘルプデスクの対応時間が圧迫されます。
課題②対応が属人化し、担当者に負担が集中する
「この人にしかわからない」
「担当がいないと対応できない」
といった属人化も深刻です。
対応の判断やノウハウが担当者個人に依存していると、
休暇時や退職時に業務が滞るリスクがあります。
特定の担当者に負荷が集中すると、
慢性的な残業やモチベーション低下を招くことも少なくありません。
課題③問い合わせ対応に追われて本来の業務が滞る
社内ヘルプデスクの業務時間の大半が、
メール・チャット・電話での対応に費やされるケースもあります。
結果として、
分析・改善など本来の価値創出業務に手が回らない状態になってしまいます。
特に年末や新年度などの繁忙期には、
対応件数が1.5〜2倍に膨らむこともあり、
運用体制の限界が露呈します。
▼ 社内ヘルプデスクの繁忙期の課題はコチラ ▼
社内ヘルプデスクの運用を成功させるためのステップ

課題の多い社内ヘルプデスク運用も、
正しい手順で改善すれば確実に効率化することができます。
重要なのは、
場当たり的な対応ではなく「仕組みとして続く運用」をつくることです。
ここでは、持続的に定着させるための3つのステップを紹介します。
STEP1:小さく始めて、成功体験を共有する
社内ヘルプデスクの改善では、
最初から全社導入を目指すと負荷が高く、現場の混乱を招くことも少なくありません。
まずはスモールスタートで運用の型をつくることが重要です。
問い合わせが多い「ITサポート」や「人事・総務」など、
特定カテゴリに絞って試験的に運用を始めましょう。
この段階では、
FAQツールやチャットボットなどの仕組みを使いながら、
どんな質問が多いのか、どの回答が効果的なのかを検証します。
例えば、1か月運用して
「FAQ経由で自己解決した件数」
「対応時間の削減率」などを数値で可視化すれば、
早期に成果を確認できます。
こうした小さな成功体験を見える形で共有することが、
社内理解と協力を得る第一歩です。
「問い合わせが30%減った」
「新人でも対応できるようになった」など、
具体的な実績を社内ミーティングや報告書で発信すれば、
他部署の参加意欲も高まり、全社展開へとつながります。
STEP2:現場の声を取り入れた改善サイクルを回す
運用を形だけ整えても、
現場が「使いにくい」と感じれば定着しません。
重要なのは、利用者の声を反映しながら改善を繰り返すことです。
たとえば月1回のレビューで、
対応ログやFAQの閲覧数、未解決件数を確認し、
「どんな質問が増えているか」
「どの回答が役立っていないか」
を定期的に分析します。
改善の際は、担当者だけで判断せず、
実際に利用する社員からのフィードバックを取り入れましょう。
「検索しづらい」
「言葉がわかりにくい」
などの意見を反映することで、
より現場に即したヘルプデスク運用ができます。
ナレッジの蓄積は“鮮度”が命です。
情報を更新し続けることで、問い合わせ対応の質も向上し、
社員の満足度や信頼感が高まります。
こうした小さな改善の積み重ねが、運用を文化として根づかせる鍵です。
STEP3:継続運用を支える“見える成果指標”を設定する
社内ヘルプデスク運用を長く続けるためには、
成果を「見える化」することが欠かせません。
対応件数や一次解決率、
FAQの参照数といった具体的なKPI(重要業績指標)を設定し、
定期的に数値を確認することで、
取り組みの効果が明確になります。
例えば、ある企業の社内ヘルプデスクでは
FAQツール整備後に一次解決率が40%から75%に向上しました。
対応担当者の負担が軽減され、
他業務への時間も確保できるようになりました。
このように、定量的な成果を把握できると、
運用チームのモチベーションも維持しやすくなります。
また、数値の変化を社内に共有することで、
「この仕組みは効果がある」という共通認識が広まり、
組織全体の協力体制が強化されます。
成果を数字で伝える仕組みを整えることが、
継続的な運用と改善のサイクルを支える柱となるのです。
▼ 社内ヘルプデスクにおすすめの「ナレッジ共有ツール」の紹介はコチラ ▼
社内ヘルプデスクを効率化する3つのポイント

効率化は単なる“時短”ではなく、
“価値ある業務に集中するための仕組み化”です。
ここでは、ヘルプデスクを根本から変える
効率化のための3つのポイントを紹介します。
✓問い合わせ情報を“見える化”し、課題を特定する
まずは現状の把握から始めましょう。
問い合わせ内容・対応時間・再発頻度などを定量的に分析することで、
どの分野に課題が集中しているかが明らかになります。
Excelやスプレッドシートで記録するだけでも、
改善への第一歩になります。
✓FAQの整備で“自己解決できる仕組み”をつくる
「質問する前に自分で調べる文化」を根づかせるには、
わかりやすく整備されたFAQが不可欠です。
カテゴリ別・タグ別に整理し、検索性を高めることで、
問い合わせ件数の削減と対応スピードの向上が同時に実現します。
FAQを活用する企業では、
問い合わせ件数が30〜50%削減された事例もあります。
✓FAQツールへの連携で対応の自動化を進める
社内ヘルプデスクで利用しているシステムと
FAQツールを連携させることで、
対応フローを自動化することができます。
例えば、
Slackや各種社内ツールからの質問に対し、
自動でFAQを提案する機能を使えば、
1件あたりの対応時間を半減することが可能です。
担当者はより高度な対応に集中できるようになります。
効率化を支える仕組みとしてFAQツールを活用する

社内ヘルプデスクの運用を効率化するために
課題を解決できる最も効果的な方法が、
FAQツールの活用です。
ここでは、
FAQツールが社内ヘルプデスクの運用にもたらす具体的な効果と、
クラウド型FAQツール「ナレッジリング」で実現できる仕組みを紹介します。
FAQツールが解決する社内ヘルプデスクの3つの課題
FAQツールは、
①ナレッジ共有不足
②属人化
③対応工数の増加
という、社内ヘルプデスクの3つの課題をまとめて解決します。
FAQ化された情報が検索・参照しやすくなることで、
社員自身が自己解決できる環境が整います。
また、検索ログの分析により
「どんな質問が多いか」を把握できるため、
改善のPDCAも回しやすくなります。
“ナレッジリング”で実現する効率化の流れ
クラウド型FAQツール「ナレッジリング」は、
現場の運用を止めずに導入・定着できる点が特長です。
ナレッジリングを導入している企業では、
1か月でFAQの閲覧率が3倍になり、
問い合わせ件数が約40%減少しました。
さらに「社内ツールとの連携」などの機能により、
運用担当者の負荷も大幅に軽減されています。
データ活用が容易な管理画面で、
FAQの改善サイクルも自走化できるため、
社内ヘルプデスクの継続的な業務効率化が実現します。
▼ 他社の成功事例を見てみる ▼
社内定着のコツは“更新の仕組み化”にある
FAQを整備しても、更新されなければ意味がありません。
ナレッジリングでは、
FAQの更新履歴や閲覧数を可視化できるため、
「見られているコンテンツ」から優先的に改善する運用が可能です。
また、部門ごとに管理者を設定し、
更新フローを自動通知することで、
情報の鮮度を維持することができます。
社内ヘルプデスクのツールとして
ナレッジリングを導入することで、
常に最新のFAQを更新し続けられる仕組みを整えられます。
機能詳細を知りたい方は、
以下から資料をダウンロードしてみてください。
▼ 30秒で完結!ナレッジリングの資料請求はコチラ ▼
まとめ
社内ヘルプデスクの課題は、
ナレッジ共有不足や属人化など、運用面の課題が中心です。
しかし、効率化を単なる時短ではなく「仕組みの改善」として捉えることで、
業務の質とスピードを両立できます。
特にFAQツールを活用すれば、
問い合わせ対応の自動化・ナレッジの可視化・継続的な改善が可能になります。
「ナレッジリング」は、
そうした課題を現場主導で解決できる仕組みを備えたツールです。
社内ヘルプデスク運用に課題を感じている方は、
ぜひ一度導入を検討してみてください。