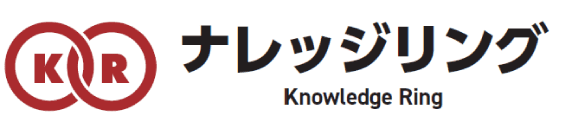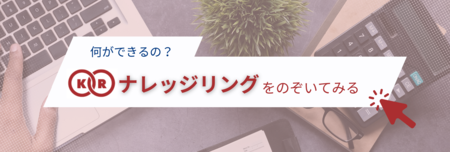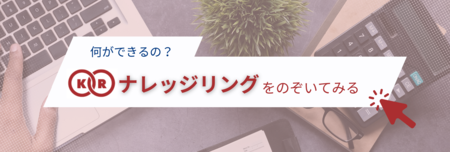属人化はなぜデメリットが大きいのか?
原因と解消策をわかりやすく紹介

こんにちは。
ナレッジリングのマーケティング担当の谷知です。
企業活動において「属人化」は避けて通れない課題のひとつです。
特定の社員に業務が集中し、
ノウハウや知識がその人しか理解していない状態が続くと、
日常業務は回っていても大きなリスクを抱え込むことになります。
さらに、急な休職や退職、担当変更の場面になると、
業務が停滞するだけでなく、
教育や情報共有が進まないことで組織の成長スピードが落ちるという
デメリットも生じます。
本記事では、
属人化がもたらすデメリットや原因を整理し、
効果的に解消するための考え方や具体策を解説します。
- 直感的なデザインで誰でもカンタンに操作できる!
- 業界最安クラスだから導入しやすい!
- 導入後もサポート付きで安心!
機能の特徴や導入事例をご紹介しております。無料プランやデモもご用意しておりますので、ぜひご覧ください。
属人化とは?その意味と現場での実例を紹介

属人化とは「業務が特定の個人に依存してしまう状態」を指し、
企業の規模や業種を問わず発生する問題です。
小規模な組織では、担当者が少ないために、
多くの業務を一人で抱え込んでしまい、
属人化が起こりやすい状況になります。
ただ、大企業でも部署ごとの専門性が高まることで
知らず知らずのうちに属人化が進行してしまいます。
特に日本企業では、
暗黙知を重視する文化や「OJTで学ぶ」慣習が強いため、
属人化が温存されやすい傾向があります。
ここでは定義や特徴、具体的なシーンを例に挙げて解説します。
属人化の定義と特徴
属人化とは、
業務や知識、スキルが特定の個人に集中し、
他の社員が代替できない状態を指します。
属人化した状態は、
担当者が不在になると業務が停滞したり、
情報がブラックボックス化したりする特徴があります。
さらに、属人化が進むと、
業務フローやマニュアルが整備されず、
属人依存が組織文化として固定化してしまうことがあります。
その結果、
社員の交代や休暇時に大きな混乱が起こりやすくなり、
組織全体の効率低下やトラブルリスク増加の一因になります。
まずは属人化の状態を理解することが、
属人化解消にもつながるのです。
属人化の典型的な業務シーン
属人化は、日常業務の中でさまざまなシーンに現れます。
例えば、
特定の担当者しか使えないシステムや、
個人の暗黙知で回っている手続き、
過去の経験則に基づく対応などが典型例です。
また、マニュアルが存在しても更新されず、
担当者の判断に依存している場合も属人化が進んでいるサインです。
結果として、
新入社員や他部署のメンバーは業務に関わることができず、
業務負荷や問い合わせが特定の社員に集中します。
こうした状況を放置すると、
属人化は固定化し、
組織全体の生産性低下やリスク増大という
組織にとってのデメリットにつながります。
属人化と情報共有不足の違い
属人化と情報共有不足は似て非なる問題です。
情報共有不足は、
「単に必要な情報やナレッジが組織内で伝わっていない状態」を指します。
一方、属人化は
「特定個人に業務や知識が集中し、
本人不在時に業務が停滞する状態」です。
情報共有があっても、属人化が進んでいる場合、
暗黙知や個人スキルが組織に定着せず、
代替が困難なままです。
つまり、
情報共有不足は「伝達不足」、
属人化は「依存構造の固定化」と理解すると整理しやすく、
解消方法を検討する際にも役立ちます。
属人化がもたらすデメリット

属人化は、
一見すると担当者の専門性を活かしている方法に感じてしまうでしょう。
しかし実際には、
業務効率の低下や引き継ぎ負担の増加、トラブル時のリスク拡大など、
組織全体に深刻な悪影響を及ぼします。
さらに、
社員のストレス増加や離職率の上昇といった人的リスクにも直結します。
表面的に見えにくいため軽視されがちですが、
中長期的には企業の競争力を大きく損なう要因です。
次の章では、
属人化が企業にとってどのようなデメリットをもたらすのかを具体的に解説します。
デメリット①業務効率の低下と遅延
属人化の最大のデメリットは、
業務効率の低下です。
特定の社員に業務が集中すると、
他の社員はその業務を代行できないため、
タスクが滞ってしまいます。
また、属人化した業務は個人のやり方に依存するため、
標準化が進まず、業務フローが複雑化しやすくなります。
その結果、情報伝達や作業の重複、
承認遅延などが頻発し、組織全体の生産性が落ちてしまいます。
属人化は業務のスピードと品質の両方を損なう原因となるのです。
デメリット②引き継ぎ・教育の負担増
属人化が進むと、
新しい担当者への引き継ぎや教育の負担が増大します。
業務の手順やノウハウが個人に依存している場合、
文書化やマニュアル整備が不十分であるため、
伝達には多大な時間と労力がかかります。
その結果、教育担当者や既存社員の負担が増え、
他業務への影響も避けられません。
また、将来的に人材が育たないという重大なデメリットも発生します。
加えて、知識の共有が進まないこと自体が、
属人化を強化する原因となってしまいます。
▼ 業務引継ぎのより具体的な課題解決はコチラ ▼
デメリット③トラブル発生時のリスク拡大
属人化した業務は、
トラブルが発生した際にリスクが顕著に現れます。
特定社員しか理解していない業務プロセスや判断基準があると、
担当者不在時には対応が困難です。
例えば、顧客からの問い合わせや緊急対応が必要な場合、
属人化している業務は滞留し、タスクが増加したり、
クレームにつながってしまう恐れがあります。
また、属人化による判断基準のブラックボックス化は、
問題解決のスピードを遅らせ、
組織全体の信頼性低下にもつながります。
このようなデメリットを軽減するためにも、
解消方法として業務の標準化やナレッジ共有が欠かせません。
デメリット④社員のストレスと離職リスク
属人化は、特定の社員に業務負荷が集中するため、
ストレスや疲弊を招きやすくなります。
責任が個人に偏り、
他メンバーが代替できない状況は心理的負担を増大させ、
モチベーション低下や離職リスクにつながります。
また、組織全体としても、
属人化によって業務が不透明になり、
社員間の不公平感や不満が生まれる場合があります。
これらのデメリットを放置すると、
人材の流出だけでなく、
組織文化やチームワークにも悪影響が及びます。
このように属人化は、
離職や異動といった避けられない出来事をきっかけに、
大きなリスクを現実化させる原因になるのです。
デメリット⑤顧客満足度への影響
属人化は社内業務にとどまらず、
顧客満足度にも影響を及ぼします。
特定の社員しか顧客情報や対応履歴を把握していない場合、
その人が不在になると対応の質が低下し、
問い合わせへのレスポンスが遅れることがあります。
これにより顧客からの信頼が損なわれ、
長期的な取引停止や評判悪化につながる恐れがあります。
顧客視点で見れば
「誰に当たっても同じ水準の対応ができること」が理想です。
属人化を解消することは、
顧客からの信頼度を安定させ、ブランド価値を守るためにも不可欠なのです。
属人化が発生する主な原因

属人化は偶然に起こるものではなく、
組織の仕組みや文化が要因となって生まれます。
マニュアルや手順書が整備されていなかったり、
情報共有の場が不足していたりすると、
必然的に担当者しか知らない「暗黙知」が増えていきます。
また、高度な専門スキルを持つ社員が業務を抱え込み、
ブラックボックス化することも珍しくありません。
ここでは、属人化を生みやすい主な要因を整理し、
解消への第一歩を考えます。
マニュアルや仕組み不足
属人化の大きな原因は、
マニュアルや業務フローといった仕組みが整備されていないことです。
手順が明文化されていないと、
特定の担当者の経験や暗黙知に依存する形になり、
他の社員は業務を代行できません。
仕組み不足は、業務の属人依存を固定化し、
新人教育や引き継ぎの負担を増大させます。
解消するには、
業務フローの可視化やマニュアル作成を進め、
誰でも対応できる環境を整備することが不可欠です。
個人スキルのブラックボックス化
特定社員のスキルやノウハウが組織内で共有されず、
ブラックボックス化することも属人化の原因です。
例えば、
個人が独自に管理しているデータやツール操作法は、
本人以外が利用できません。
これにより、担当者が不在の場合、
業務が停滞しやすくなります。
解消のためには、
知識の見える化や共有手段の整備、
定期的な情報更新を行い、
個人依存から組織依存への移行が必要です。
情報共有の文化が弱い
属人化は、
情報共有の文化が弱い組織でも発生しやすいです。
例えば、
必要な情報をチーム内で伝達しなかったり、
ナレッジを蓄積せず個人だけで管理するなどの習慣は、
属人化を加速させる要因となります。
こうした文化が根付いてしまっては、
新人や他部署から異動してきた人が業務を理解するのに時間がかかり、
組織全体の効率低下を招きます。
このような状況を解消するためには、
情報共有の重要性を組織全体で認識し、
日常的にナレッジを共有する仕組みづくりが求められます。
▼ 情報共有の具体的な課題解決はコチラ ▼
情報共有ツールで探す時間ゼロへ!今すぐ始める効率化への第一歩
属人化を放置したときのリスク

属人化は「今はなんとかなっている」からと放置されやすい課題です。
しかし長期的に放置すると、
人材流出や生産性低下、
新規プロジェクトの停滞といった重大なリスクを引き起こします。
属人化は一度進行すると解消に多大な労力がかかるため、
早期の対処が重要です。
ここでは、
属人化の放置によってどのような組織的リスクが現れるのかを具体的に見ていきます。
人材流出による業務停滞
属人化が進むと、
担当者の退職や休職が直接的な業務停滞につながります。
特定の社員に依存した業務は、
引き継ぎが不十分だと他の社員が代替できず、タスクが滞留します。
この状況はプロジェクト遅延や顧客対応の遅れを招き、
信頼性低下のリスクも高まります。
このような状況を避けるために、
日ごろから業務手順やノウハウを文書化し、
組織全体で共有することが不可欠です。
▼ ノウハウ共有による具体的な効果はコチラ ▼
ノウハウ・ナレッジの違いを徹底解説! FAQ活用で“知ってる”を仕組化する方法
組織の生産性・競争力低下
属人化は、
業務の属人依存により組織全体の生産性を低下させます。
担当者が不在時の業務停滞や、非効率な個別対応が続くと、
業務分担が困難になります。
さらに、新規プロジェクト等に割く時間が不足してしまい、
競争力低下の要因にもなります。
業務フローの標準化や情報共有ツール導入など、
仕組みを中心とした取り組みが必要です。
新規プロジェクトの停滞
属人化が解消されていない組織では、
新規プロジェクトの立ち上げや拡大が滞りやすくなります。
担当者が特定社員に依存するため、
計画策定やタスク分担に時間がかかり、意思決定も遅延します。
また、業務知識が共有されていないと、
関係者が必要な情報を迅速に取得できず、
プロジェクトの進行に影響します。
業務の可視化やナレッジ共有、教育体制の整備が不可欠です。
属人化を解消するために必要な考え方

属人化を根本から解消するためには、
単に業務手順を共有するだけでは不十分です。
組織全体で「個人依存ではなく仕組み依存へ」という考え方を
浸透させることが欠かせません。
そのためには、ナレッジマネジメントを推進し、
誰もが情報にアクセスできる仕組みを整える必要があります。
さらに、
属人化を防ぐ文化を組織風土として育むことが解消への近道となります。
ここでは、属人化解消に必要な組織の視点や文化づくりについて解説します。
「個人依存」から「仕組み依存」へ
属人化を解消する第一歩は、
業務を個人のスキルや記憶に依存させず、
仕組みやプロセスに依存させることです。
具体的には、業務フローを文書化し、
手順やルールを誰でも理解できる形で整備します。
これにより、担当者不在時でも業務が滞らず、
引き継ぎや教育負担も軽減されます。
組織全体で「仕組みで回る業務」を意識することが、
属人化解消の基本的な考え方と言えるでしょう。
ナレッジマネジメントの重要性
属人化を解消するには、
ナレッジマネジメントの導入が不可欠です。
個人の経験やノウハウを組織内に蓄積・共有することで、
誰でも業務を理解し、対応できる環境が整います。
具体的には、
FAQや社内Wikiなどで情報を整理し、
検索可能な形で提供することが有効です。
これにより、業務の属人依存を減らし、
組織全体の効率と安定性を高められます。
▼ ナレッジマネジメントの具体的な紹介はコチラ ▼
属人化解消に向けた組織文化づくり
属人化を解消するには、
ツールや仕組みだけでなく、組織文化の改革も重要です。
情報共有や標準化を推奨する文化を根付かせることで、
社員が自主的に知識を蓄積・活用する習慣が生まれます。
具体的には、
定期的な情報共有会議やナレッジ活用の評価制度を導入することで、
属人化解消に向けた組織全体の意識改革が可能です。
文化づくりは解消の成功率を高める鍵となります。
経営層が関わることの重要性
属人化解消を進めるうえで見落とされがちなのが、
経営層の関与です。
現場レベルでマニュアル作成や情報共有を進めても、
経営層が「属人化解消の重要性」を理解していなければ、
取り組みは一過性で終わってしまいます。
経営層が率先してリスク認識を示し、
リソースや予算を確保することが、
全社的な取り組みを成功させるポイントです。
属人化を経営課題として捉えることで、
現場の負担軽減と組織全体の生産性向上につながります。
属人化解消に役立つ組織的な取り組みとは

属人化の解消は、
一人ひとりの努力に任せるのではなく、
組織として仕組みを設計し運用することが重要です。
業務フローの見える化や標準化、OJTと教育体制の強化、
定期的な情報共有などは、地道ながら効果的な方法です。
これらの取り組みを組織的に進めることで、
属人化の芽を早期に摘み取ることが可能になります。
ここでは代表的な組織での取り組みを紹介します。
業務フローの見える化と標準化
属人化解消には、
業務フローの見える化と標準化が重要です。
担当者ごとに異なる手順や判断基準を整理し、
誰でも理解できる形式で文書化します。
これにより、業務の属人依存が減り、
引き継ぎやトラブル対応もスムーズになります。
また、標準化された業務フローは、
改善や効率化の基礎にもなり、
組織全体の生産性向上につながります。
OJTと教育体制の強化
属人化を防ぐには、
OJTや教育体制の強化も欠かせません。
新人や異動者に業務を教える際、
個人依存ではなく標準化されたフローやマニュアルを活用することで、
知識伝達の効率が上がります。
定期的な研修やローテーションを組み合わせることで、
特定社員だけに業務が偏らず、
組織全体のスキル底上げが可能です。
定期的な情報共有ミーティング
定期的な情報共有ミーティングは、
属人化解消に有効です。
業務の進捗や課題、
成功事例をチーム内で共有することで、
知識が個人に偏ることを防げます。
また、ミーティングで得た情報をナレッジベースに蓄積することで、
後からでも参照可能になり、業務の属人依存を減らせます。
日常的に情報を更新・共有する習慣が、
属人化解消につながります。
▼ ナレッジベースの具体的な解説はコチラ ▼
ナレッジベースとは?構築のメリットとツールとしての活用アイデアをご紹介
属人化解消に有効なツールの活用方法

近年ではITツールを活用することで、
属人化の解消を効率的に進められるようになりました。
FAQシステムやマニュアル作成ツール、
社内Wikiといった仕組みを導入すれば、
知識を共有しやすく、
誰でも業務を再現できる環境が整います。
ただし、ツールを導入するだけでは成果は出ません。
運用ルールの設計や習慣化が重要です。
ここでは代表的なツールの活用方法を解説します。
FAQシステムによる「自己解決率」向上
FAQシステムを導入すると、
社員が自分で疑問を解決できる「自己解決率」が向上します。
これにより、
属人化の原因である「特定の人に頼る文化」を改善することができます。
FAQシステムを導入することにより、
属人化した業務知識やノウハウを整理・公開することで、
問い合わせや依存を減らせます。
また、検索性が高いシステムなら、
必要な情報に即アクセス可能です。
これにより、特定社員に業務が集中することを防ぎ、
ナレッジが組織全体に定着します。
FAQシステムは、
属人化解消のためのツール活用の中核となります。
▼ 属人化の解消としてFAQシステムを使う具体的な方法はコチラ ▼
マニュアル作成ツールでの効率化
マニュアル作成ツールを活用すると、
業務手順やナレッジを効率的に整理・更新できます。
従来の紙やExcelでの管理では更新が追いつかず、
属人化が進む原因になりがちです。
ツールを使えば、
テンプレートやガイドラインに沿って誰でも簡単に文書化でき、
最新情報を共有できます。
効率的に文書を作れるため、
更新が滞るというデメリットも防げます。
また、検索機能やアクセス権管理を活用すれば、
必要な情報を必要な人が迅速に取得でき、
業務効率の向上と属人化解消の両立が可能です。
社内Wiki・ナレッジベースの活用と課題
社内Wikiやナレッジベースも、
情報共有と属人化解消に有効です。
業務マニュアルやQ&Aを蓄積することで、
誰でも参照可能になり、
特定社員に依存しない環境を作れます。
ただし、更新が滞ると情報が古くなり、
逆に属人化や混乱を招くリスクがあります。
運用ルールを整備し、
定期的なレビューや責任者の明確化が重要です。
適切に運用すれば、
組織全体のナレッジ活用が促進されます。
ツール導入時の注意点
属人化解消ツールを導入する際には、
目的や運用体制を明確にすることが不可欠です。
ツールはあくまで手段であり、
導入すれば自動的に属人化が解消されるわけではありません。
運用ルールが不十分だと情報が更新されず、
かえって混乱を招くこともあります。
また、社員が操作しやすいツールかどうかという点も
ツール導入成功の分かれ道です。
導入時には
「どの業務を標準化するか」
「誰が情報を更新するか」を具体的に決めることが、
継続的な成果につながります。
属人化解消の決め手!FAQシステム「ナレッジリング」

数ある属人化解消の手段の中でも、FAQシステムは特に効果的です。
社員が疑問を自己解決できる環境を整えることで、
特定の人に質問が集中する事態を防ぎます。
さらにFAQシステムは、属人化の解消だけでなく、
教育コスト削減や業務効率化にも大きく寄与します。
なかでも「ナレッジリング」は、
使いやすさと機能性を兼ね備えたFAQシステムとして注目されています。
ここでは「ナレッジリング」の特徴と導入効果を解説します。
属人化を解消できるFAQ型情報共有のメリット
FAQ型の情報共有は、
個人依存の業務知識を組織全体で活用できる形に整理します。
ナレッジリングのようなツールを使うと、
誰でも検索・参照可能な形でFAQが蓄積され、
担当者不在時でも業務が滞りません。
これにより、属人化によるトラブルや負荷を減らし、
組織全体の業務効率と安定性を向上させることができます。
また、情報更新や参照履歴を可視化できるため、
ナレッジ活用の改善にもつながります。
ナレッジリングの特徴と導入効果とは
ナレッジリングは、
FAQ型情報共有に特化したクラウドシステムで、
検索性・分類機能・アクセス権管理が充実しています。
ナレッジリングを導入することで、
属人化した業務知識が組織全体で活用でき、
問い合わせ対応の効率化や自己解決率の向上が見込めます。
さらに、更新や改善の履歴が残るため、
ナレッジの鮮度が保たれ、
組織全体での知識定着が促進されます。
属人化解消事例に学ぶナレッジリング導入事例
ナレッジリングを活用した属人化解消事例では、
まず業務プロセスの整理とFAQ化が多く挙げられています。
社員がアクセス・更新できる仕組みを構築し、
定期的に情報をレビューする運用を徹底することで、
問い合わせ件数の減少や教育時間の短縮、
業務引き継ぎのスムーズ化につながっています。
ナレッジリング導入成功のポイントは、
単に導入するだけでなく、
運用ルールと組織文化をセットで整備することと言えるでしょう。
▼ 他社の成功事例を見てみる ▼
属人化を解消し「仕組みで回る組織」へ
ナレッジリングを導入することで、
属人化を解消して「仕組みで回る組織」を目指すことが可能です。
ナレッジリングを導入し、属人化解消の仕組みを作ることで、
個人の経験やスキルを組織知として定着させ、
担当者不在でも業務を滞らせず、
業務効率や安定性が向上していきます。
また、ナレッジ共有の仕組みが浸透すると、
新人教育や引き継ぎも効率化され、
組織全体のパフォーマンスが底上げされます。
属人化解消の最終ゴールは、
仕組み中心の安定した業務運営を実現することです。